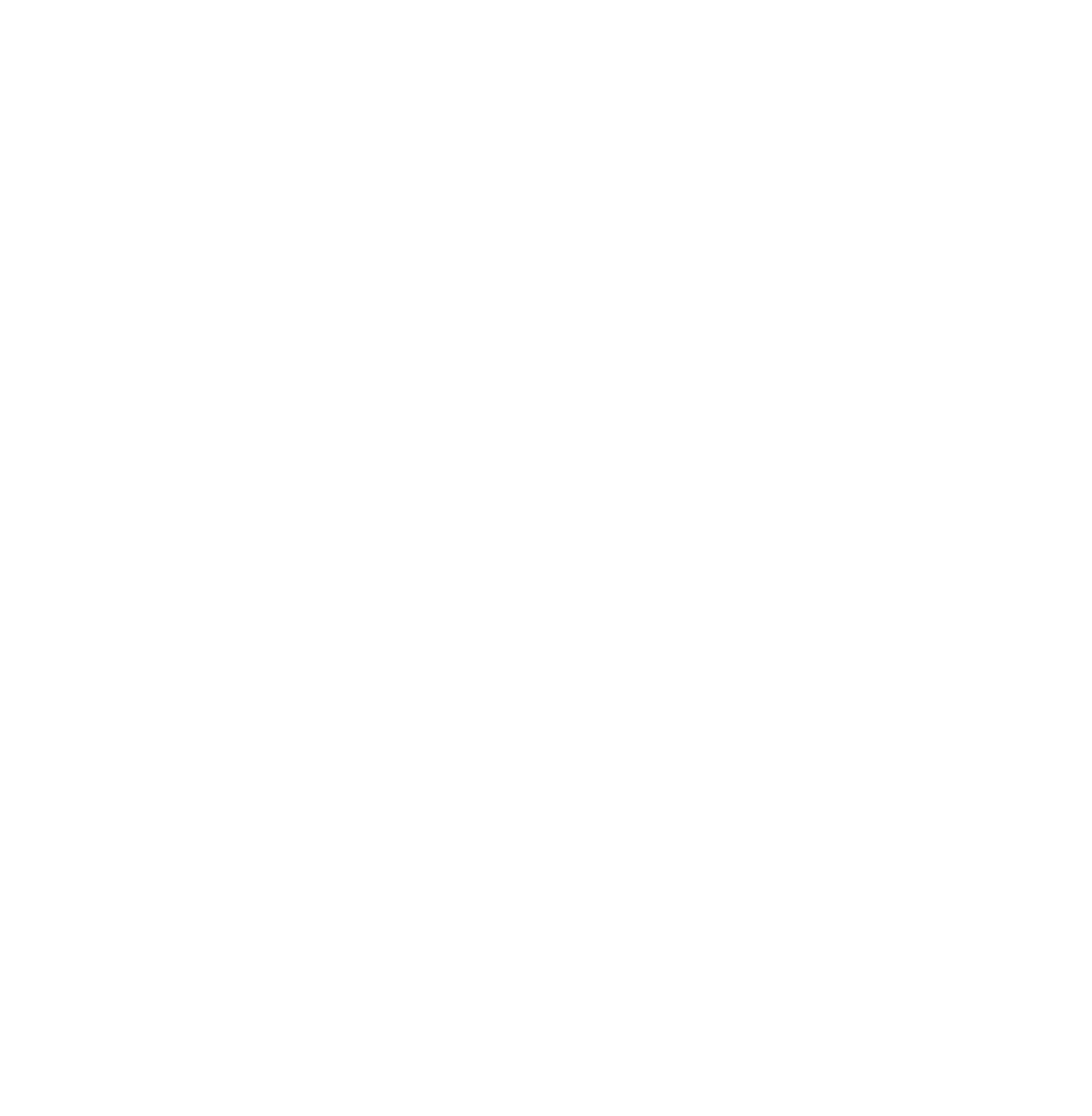ブログ
2025-05-11 10:43:15
民法883条(相続開始の場所)
🏡 相続は「どこで」始まる?――民法第883条と相続税の深い関係
こんにちは、中村裕史税理士事務所です😊
今回は少しマニアックだけどとっても重要な法律、民法第883条「相続開始の場所」について解説します。
「相続はいつ始まるか?」というタイミングも大切ですが、実は「どこで始まるか」も、相続手続きや税金に大きく関わってくるんです!
📘 民法第883条とは?
第883条(相続開始の場所)
相続は、被相続人の住所において開始する。
つまり、誰かが亡くなったとき、その人の「住所」が、相続のスタート地点=相続開始の場所になるということです。
🧭 なぜ「相続開始の場所」が大事なの?
この場所が決まると、次のような手続きの提出先が決まります。
相続税の申告 …亡くなった方の住所地を所轄する税務署
💡 よくある誤解
「自分(相続人)の住まいの近くの税務署に出せばいいのでは?」
→ ❌違います!
「相続人が複数いる場合、それぞれが地元の税務署に出すの?」
→ ❌全員分まとめて、被相続人の住所地の税務署へ提出!
遺言の検認など…住所地を管轄する家庭裁判所
除籍謄本の取得 …最後の住所地の市区町村役場
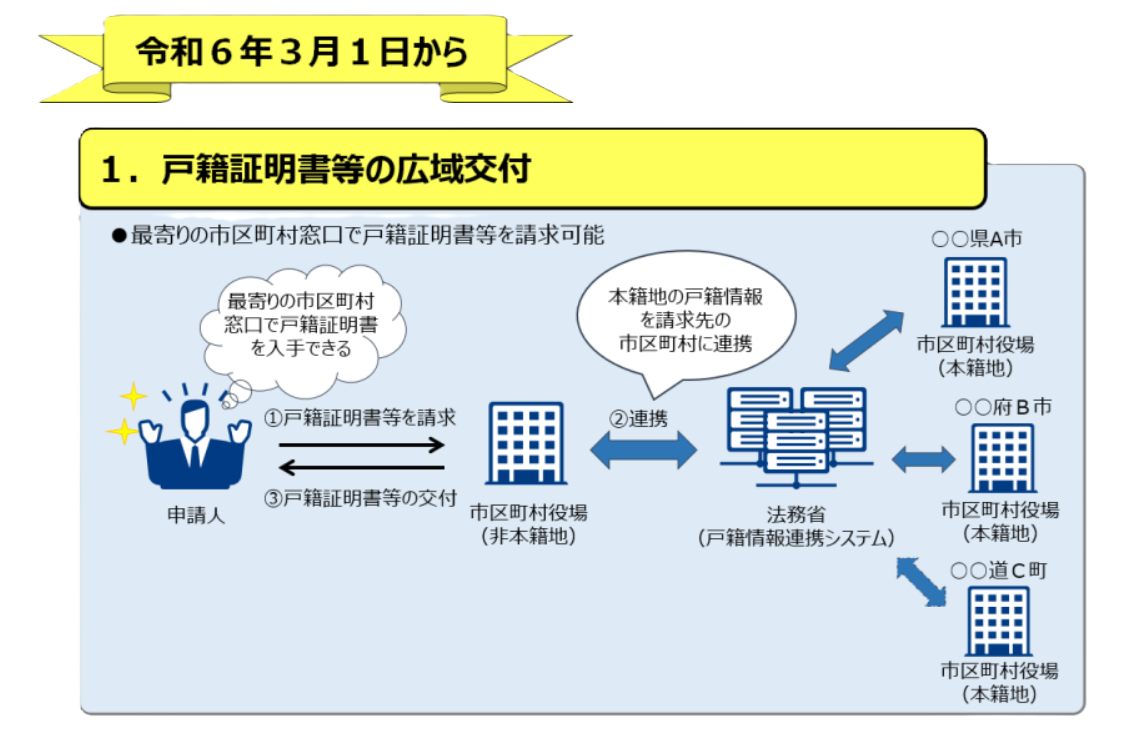
法務省HPより引用
但し請求者は本人、配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)に限られます。
不動産登記(相続登記)…不動産の所在地を管轄する法務局
住所が東京都なのか千葉県なのかで、提出先が変わってしまうのです😲
🏠「住所」って住民票の場所のこと?
✅ 原則は住民票のある場所ですが、
実際には「生活の本拠だったかどうか」が判断基準になることもあります(;´Д`A ```
💡 たとえばこんなケース…
📍 Case1:東京に住民票があるけど、大阪で暮らしていた
→ 実態によっては「大阪」が住所とされる可能性も。
📍 Case2:国内に住民票があるけど、海外居住期間が長い
→ 「生活の本拠地」かどちらかがポイントに。
📍 Case3:施設に長期入所中で自宅は空き家
→ 「やむを得ない事由」があるかどうかがポイントに。
💰 特例にも関係する!相続税と住所の深いつながり
実はこの「住所」、相続税の特例にも影響大なんです!
🏠 小規模宅地等の特例
→ 被相続人が住所として使っていた自宅の土地なら、相続税の評価を最大80%評価減の対象に✨
でも、賃貸住宅に住んでいたなどで「もはや住んでいなかった」とされると…適用NGになる可能性も💦
🛏 配偶者居住権の特例
→ 「夫婦で住んでいた家=住所」でないと、そもそもこの制度が使えません。
🌍 海外に住んでいた場合は?
被相続人が外国在住(非居住者)だった場合、
相続税の課税対象や適用できる特例が大きく変わります!
住所が日本…全世界財産に課税
住所が海外…日本国内の財産に限って課税(ただし例外あり)
✅ まとめ
民法883条の「住所」とは、生活の本拠のこと🏡
相続税の申告先、特例適用、家庭裁判所などの手続きはすべてこの住所に基づく!
ただし、住民票と異なる実態がある場合は、特例適用の可否に影響があるために慎重な判断が必要💡
📞 ご相談ください!
「うちの場合、どこが住所になるの?💦」
「小規模宅地の特例は受けられる?」
そんな疑問があれば、お気軽にご相談ください!
👉 相続まるごとサポートも実施中!
👉 相続税の申告、名義変更、遺言対応もすべてお任せください✨
民法883条(相続開始の場所)
『条文内容』
(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。
(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。
🏡 相続は「どこで」始まる?――民法第883条と相続税の深い関係
こんにちは、中村裕史税理士事務所です😊
今回は少しマニアックだけどとっても重要な法律、民法第883条「相続開始の場所」について解説します。
「相続はいつ始まるか?」というタイミングも大切ですが、実は「どこで始まるか」も、相続手続きや税金に大きく関わってくるんです!
📘 民法第883条とは?
第883条(相続開始の場所)
相続は、被相続人の住所において開始する。
つまり、誰かが亡くなったとき、その人の「住所」が、相続のスタート地点=相続開始の場所になるということです。
🧭 なぜ「相続開始の場所」が大事なの?
この場所が決まると、次のような手続きの提出先が決まります。
相続税の申告 …亡くなった方の住所地を所轄する税務署
💡 よくある誤解
「自分(相続人)の住まいの近くの税務署に出せばいいのでは?」
→ ❌違います!
「相続人が複数いる場合、それぞれが地元の税務署に出すの?」
→ ❌全員分まとめて、被相続人の住所地の税務署へ提出!
遺言の検認など…住所地を管轄する家庭裁判所
除籍謄本の取得 …最後の住所地の市区町村役場
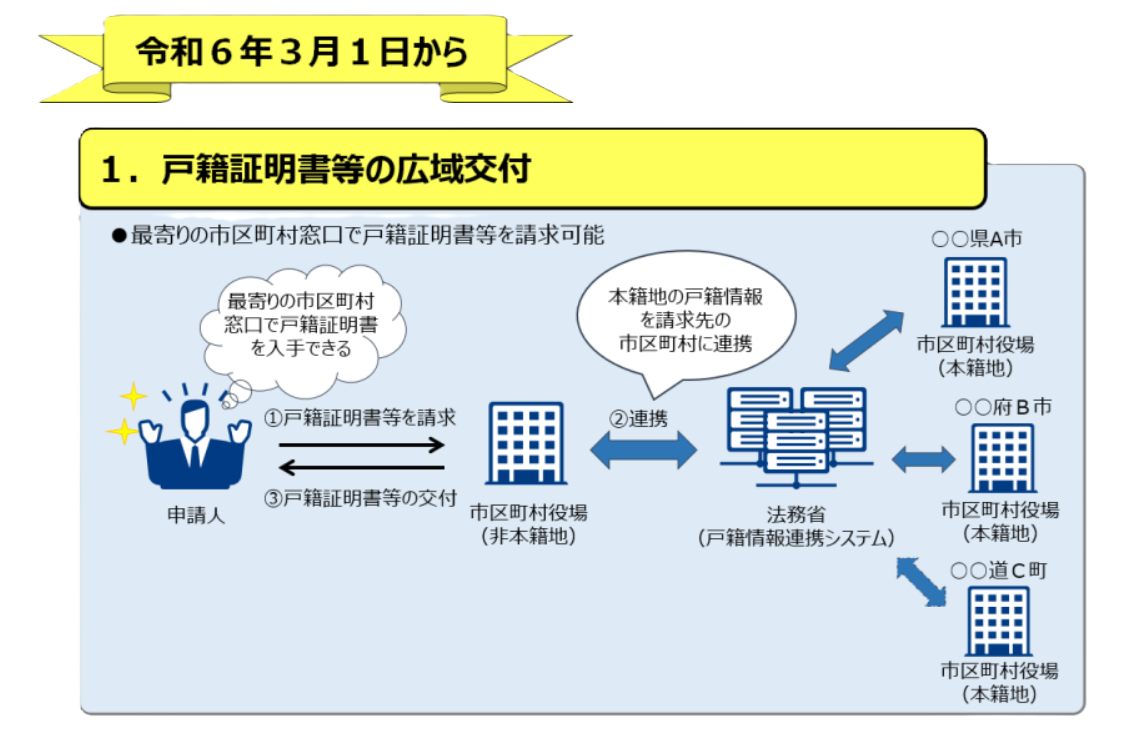
法務省HPより引用
但し請求者は本人、配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)に限られます。
不動産登記(相続登記)…不動産の所在地を管轄する法務局
住所が東京都なのか千葉県なのかで、提出先が変わってしまうのです😲
🏠「住所」って住民票の場所のこと?
✅ 原則は住民票のある場所ですが、
実際には「生活の本拠だったかどうか」が判断基準になることもあります(;´Д`A ```
💡 たとえばこんなケース…
📍 Case1:東京に住民票があるけど、大阪で暮らしていた
→ 実態によっては「大阪」が住所とされる可能性も。
📍 Case2:国内に住民票があるけど、海外居住期間が長い
→ 「生活の本拠地」かどちらかがポイントに。
📍 Case3:施設に長期入所中で自宅は空き家
→ 「やむを得ない事由」があるかどうかがポイントに。
💰 特例にも関係する!相続税と住所の深いつながり
実はこの「住所」、相続税の特例にも影響大なんです!
🏠 小規模宅地等の特例
→ 被相続人が住所として使っていた自宅の土地なら、相続税の評価を最大80%評価減の対象に✨
でも、賃貸住宅に住んでいたなどで「もはや住んでいなかった」とされると…適用NGになる可能性も💦
🛏 配偶者居住権の特例
→ 「夫婦で住んでいた家=住所」でないと、そもそもこの制度が使えません。
🌍 海外に住んでいた場合は?
被相続人が外国在住(非居住者)だった場合、
相続税の課税対象や適用できる特例が大きく変わります!
住所が日本…全世界財産に課税
住所が海外…日本国内の財産に限って課税(ただし例外あり)
✅ まとめ
民法883条の「住所」とは、生活の本拠のこと🏡
相続税の申告先、特例適用、家庭裁判所などの手続きはすべてこの住所に基づく!
ただし、住民票と異なる実態がある場合は、特例適用の可否に影響があるために慎重な判断が必要💡
📞 ご相談ください!
「うちの場合、どこが住所になるの?💦」
「小規模宅地の特例は受けられる?」
そんな疑問があれば、お気軽にご相談ください!
👉 相続まるごとサポートも実施中!
👉 相続税の申告、名義変更、遺言対応もすべてお任せください✨