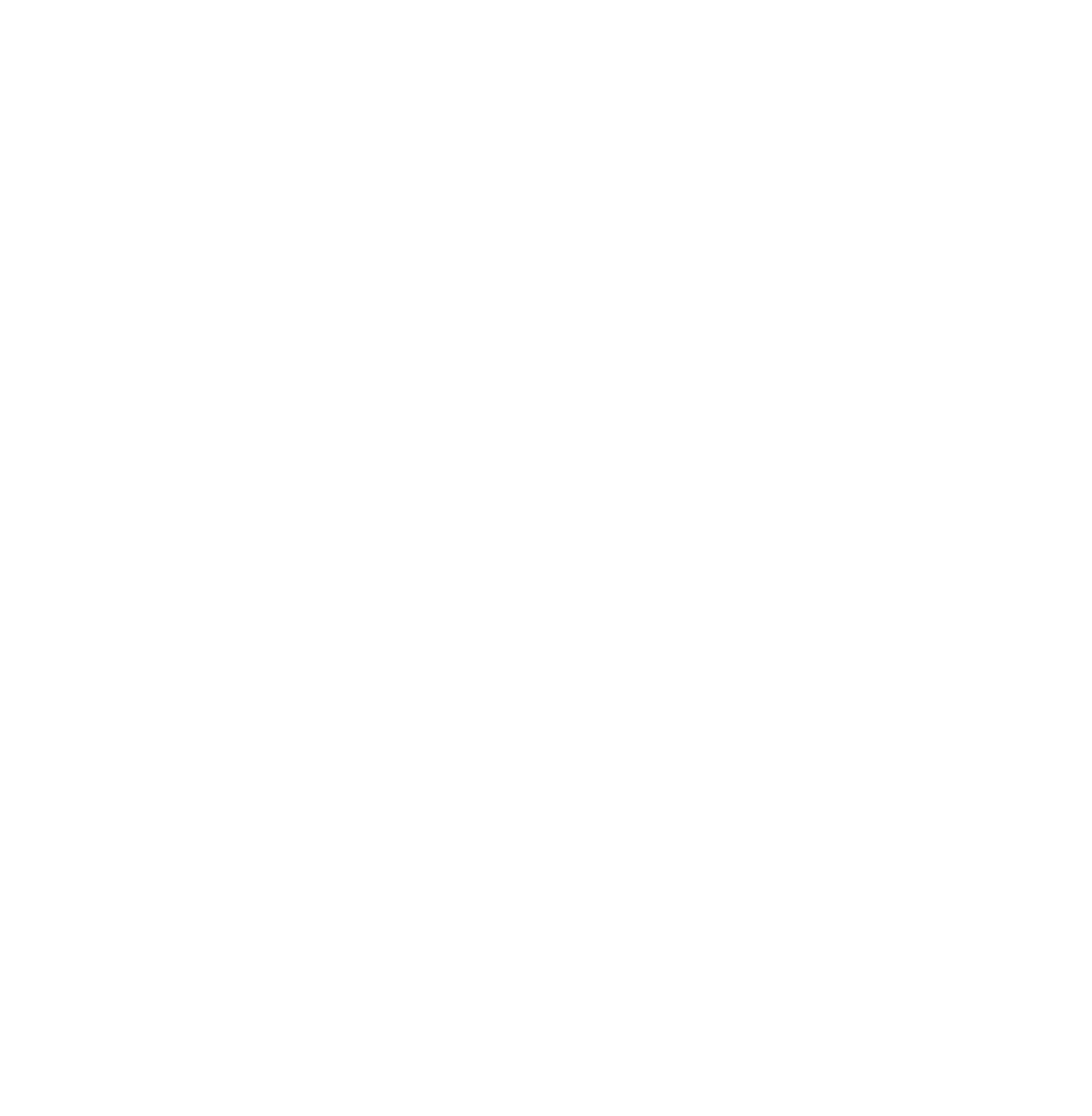ブログ
2025-05-12 13:20:25
民法884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、下記のいずれか早い時期に時効により消滅します(´ω´)ノ
① 相続人またはその法定代理人が、相続権を侵害された事実を知った時から5年行使しないとき
② 相続開始から20年を経過したとき
つまりこの条文は、「いつまでに相続権を回復する訴えを起こさなければならないか」という時効の期限を定めています。
✅ 用語整理
相続回復請求権:本来の相続人が、自分の相続権を侵害している人に対して「それは自分の権利だ」と主張し、返還等を求める権利となります。
相続権の侵害:他人が不当に相続人の地位を占有し、財産を取得してしまうこと。
🔍
■ 例1:他人が相続人を装って遺産を相続
事案:
被相続人Aが死亡(2000年)した。本来の相続人は子BであるがAの兄Cが「自分が相続人だ」と主張して、遺産(不動産)を相続登記してしまう。Bは2022年にこの事実を初めて知る。
上記の場合、相続回復請求権はどうなるか?
「知った時=2022年」から5年以内 の2027年までに請求できる。
ただし、「相続開始=2000年」から20年 である2020年に時効完成。
✅ よって、Bの請求権は既に2020年に時効消滅している。
➡ このように、20年経過すると、知っていたかどうかに関係なく請求権は消滅します(これを除斥期間といいます)。
■ 例2:早く知った場合
被相続人Aが死亡(2010年)した。本来の相続人Bが、兄Cに不動産を相続されたことを2012年に知ったが、Bが訴えを起こしたのは2018年の場合。
この場合は「知った時から5年=2017年まで」が期限
✅ 2018年では1年時効を過ぎているため請求不可
そんなことあるの❔と思われるかもしれませんが相続回復請求権が使われる具体的なケースは下記のような事例かと想定されます。
① 【親族による単独登記・排除】
相続人の一部(例えば兄)が、他の相続人(妹など)に無断で遺産分割協議書を作成(場合によっては偽造)し、単独で不動産を登記するが、後になって他の相続人がそれを知り、「自分も相続人だ」として権利回復を主張する。
➡ 実際に多く見られる「相続人の一部による排除」型。
➡ 不動産が絡むと金額も大きく、訴訟になることも。
② 【非嫡出子・認知された子どもが相続から外されていた】
生前に認知された子(婚外子)がいたが、死亡後にその存在を親族が隠し、相続に参加させなかった。しかし、認知された子が後で事実を知り、「自分にも相続権がある」と主張して回復請求。
➡ 家庭裁判所での「 認知の訴え」と並行して争われることも。
➡ 裁判所の認定後、884条に基づき回復請求がなされる。
③ 【実子とされていたが、後に無効や養子縁組取消がされた】
養子縁組が無効であったと判明し、本来の相続人でない者が遺産を取得していたが、真の相続人が相続回復請求権を用いて返還を求める。
➡ 養子縁組の手続不備などが原因。
④ 【赤の他人が虚偽の登記をした(極めて稀)】
偽造戸籍などにより相続人を装い、赤の他人が相続登記をしてしまい、悪意ある第三者が不動産を横取りした場合に、回復請求が必要。
➡ 稀だが被害が深刻になるため訴訟対応が必要。
⑤ 【遺言書があったのに、法定相続人が無視して登記した】
有効な遺言書があったにもかかわらず、法定相続人が勝手に分割協議をして登記、その後遺言で受遺者となっていた人が、「本来は自分の権利」として相続回復を請求。
➡ 遺贈と相続の区別が問題になる場合も。
ただし、法務局での登記での形式審査がある事や、884条に基づかなくとも「遺産分割協議無効確認訴訟」など他の訴訟手段で処理されることもあり、884条の行使は稀となります(゚Д゚;)
民法884条(相続回復請求権)
『条文内容』
(相続回復請求権)
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(相続回復請求権)
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
相続回復の請求権は、下記のいずれか早い時期に時効により消滅します(´ω´)ノ
① 相続人またはその法定代理人が、相続権を侵害された事実を知った時から5年行使しないとき
② 相続開始から20年を経過したとき
つまりこの条文は、「いつまでに相続権を回復する訴えを起こさなければならないか」という時効の期限を定めています。
✅ 用語整理
相続回復請求権:本来の相続人が、自分の相続権を侵害している人に対して「それは自分の権利だ」と主張し、返還等を求める権利となります。
相続権の侵害:他人が不当に相続人の地位を占有し、財産を取得してしまうこと。
🔍
■ 例1:他人が相続人を装って遺産を相続
事案:
被相続人Aが死亡(2000年)した。本来の相続人は子BであるがAの兄Cが「自分が相続人だ」と主張して、遺産(不動産)を相続登記してしまう。Bは2022年にこの事実を初めて知る。
上記の場合、相続回復請求権はどうなるか?
「知った時=2022年」から5年以内 の2027年までに請求できる。
ただし、「相続開始=2000年」から20年 である2020年に時効完成。
✅ よって、Bの請求権は既に2020年に時効消滅している。
➡ このように、20年経過すると、知っていたかどうかに関係なく請求権は消滅します(これを除斥期間といいます)。
■ 例2:早く知った場合
被相続人Aが死亡(2010年)した。本来の相続人Bが、兄Cに不動産を相続されたことを2012年に知ったが、Bが訴えを起こしたのは2018年の場合。
この場合は「知った時から5年=2017年まで」が期限
✅ 2018年では1年時効を過ぎているため請求不可
そんなことあるの❔と思われるかもしれませんが相続回復請求権が使われる具体的なケースは下記のような事例かと想定されます。
① 【親族による単独登記・排除】
相続人の一部(例えば兄)が、他の相続人(妹など)に無断で遺産分割協議書を作成(場合によっては偽造)し、単独で不動産を登記するが、後になって他の相続人がそれを知り、「自分も相続人だ」として権利回復を主張する。
➡ 実際に多く見られる「相続人の一部による排除」型。
➡ 不動産が絡むと金額も大きく、訴訟になることも。
② 【非嫡出子・認知された子どもが相続から外されていた】
生前に認知された子(婚外子)がいたが、死亡後にその存在を親族が隠し、相続に参加させなかった。しかし、認知された子が後で事実を知り、「自分にも相続権がある」と主張して回復請求。
➡ 家庭裁判所での「 認知の訴え」と並行して争われることも。
➡ 裁判所の認定後、884条に基づき回復請求がなされる。
③ 【実子とされていたが、後に無効や養子縁組取消がされた】
養子縁組が無効であったと判明し、本来の相続人でない者が遺産を取得していたが、真の相続人が相続回復請求権を用いて返還を求める。
➡ 養子縁組の手続不備などが原因。
④ 【赤の他人が虚偽の登記をした(極めて稀)】
偽造戸籍などにより相続人を装い、赤の他人が相続登記をしてしまい、悪意ある第三者が不動産を横取りした場合に、回復請求が必要。
➡ 稀だが被害が深刻になるため訴訟対応が必要。
⑤ 【遺言書があったのに、法定相続人が無視して登記した】
有効な遺言書があったにもかかわらず、法定相続人が勝手に分割協議をして登記、その後遺言で受遺者となっていた人が、「本来は自分の権利」として相続回復を請求。
➡ 遺贈と相続の区別が問題になる場合も。
ただし、法務局での登記での形式審査がある事や、884条に基づかなくとも「遺産分割協議無効確認訴訟」など他の訴訟手段で処理されることもあり、884条の行使は稀となります(゚Д゚;)