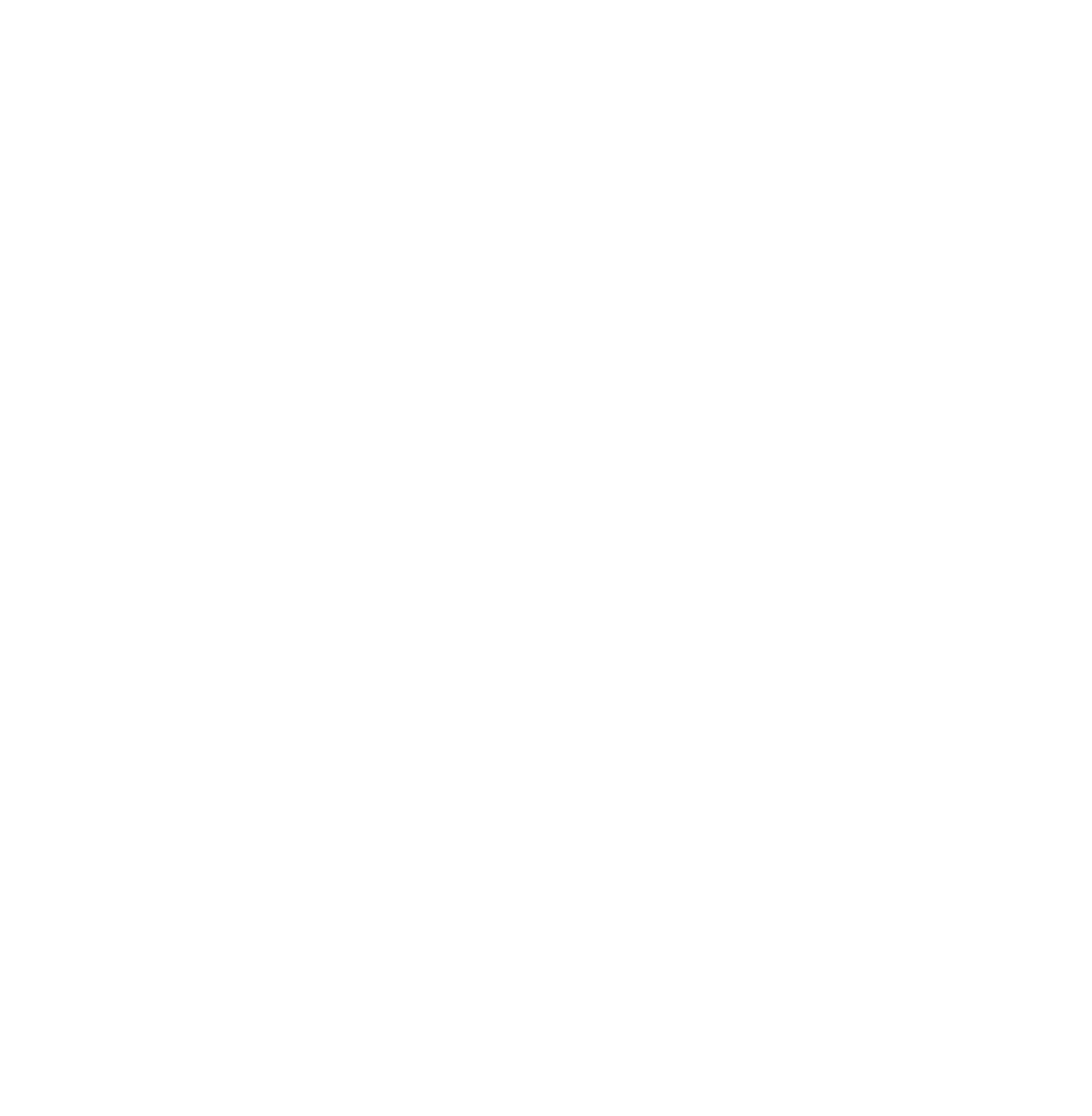ブログ
2025-05-12 19:12:08
生命保険金💰は相続財産?非課税?包括受遺者にも関係ある?
生命保険金は相続においてよく出てくるテーマですが…
「そもそも相続財産なの?」
「非課税枠って誰でも使えるの?」
「包括受遺者も対象なの?」
と、意外とややこしい点がたくさんあります🌀
今回は、民法と税法の考え方の違い、そして相続放棄や包括受遺者との関係性も交えながら、わかりやすく解説していきます!
🧾 保険金は相続財産?~民法と税法のズレ~
💬 民法では、生命保険金は被相続人の死亡によって発生するものの、「契約に基づき受取人が取得する財産」であるため、遺産分割の対象にはなりません。
💰 しかし税法では、「死亡を原因として取得する財産」は相続で取得したと“みなして”課税されます(=みなし相続財産)。
つまり、“相続財産じゃないのに相続税がかかる”という、ちょっと不思議な立場なのです😅
💸 非課税枠がある!でも使える人に条件あり
相続税法では、次の計算式で非課税枠が認められています。
✅ 500万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人いれば、1,500万円まで非課税枠が使えます。ただし、この“法定相続人”には注意が必要です⚠
なぜならこの法定相続人も民法と税法で考え方が違うのです…( ノД`)シクシク…
📘 民法における「法定相続人」
民法では、相続が発生したときに財産を相続する権利がある人を「法定相続人」といいます。
基本の優先順位は次のとおり👇
配偶者(常に相続人)
第一順位…子(または代襲相続人)
第二順位…親(直系尊属)
第三順位…兄弟姉妹(または代襲相続人)
💡相続放棄をすると、民法上は「最初から相続人でなかったもの」とみなされます(=権利喪失)。
💰 税法における「法定相続人」
一方、相続税法で用いられる「法定相続人の数」は、次のような目的に使われます。
相続税の基礎控除の計算
生命保険金や死亡退職金の非課税枠の計算
📌 このときの「法定相続人の数」は、相続放棄していてもカウントされます!
例:相続人が配偶者+子3人(うち1人が放棄)
→ 民法上の法定相続人の数:配偶者+子2人
→ 税法上の法定相続人の数:4人として計算(放棄者も含む)
㊟税法では養子の人数にも制限があります。
❌ 相続放棄をした人は非課税枠が「使えない」
相続放棄をしていても、非課税枠の「計算上の人数」には含まれます。しかし、放棄した本人が保険金を受け取った場合は🚫 非課税枠の適用は受けられません。
なぜなら、保険金を受け取るには、「相続人であること」が必要。
相続放棄した人は、最初から相続人でなかったと“みなされる”からです。
🧑⚖️ では、「包括受遺者」はどうなるの?
「包括受遺者」とは、遺言で「財産の全部」や「○分の○」など包括的に財産を譲り受ける人のことです。
民法では📌 包括受遺者は相続人と同じ義務を負う者であり相続人とほぼ同等の立場とされますが、非課税枠の適用がありません。(;´Д`)
つまり
相続人 … ✅ なる
相続放棄した人… ❌ ならない
包括受遺者 … ❌ ならない(相続人の立場でもあれば✅ なる)
📝 まとめ
生命保険金は、相続財産ではないのに課税対象になるという特例的な財産。そして、誰が受け取るかによって、非課税かどうかがガラッと変わります。
✅ 民法では「固有財産」
✅ 税法では「みなし相続財産」
✅ 相続人・ 相続人である包括受遺者には非課税枠がある
✅ 相続放棄者は非課税枠ナシ
💬 専門家のサポートを活用しよう!
ちょっとした判断ミスで、数百万円の相続税差が生じることもあります。相続税の専門家である税理士に相談するのが安心です😊
生命保険金💰は相続財産?非課税?包括受遺者にも関係ある?
生命保険金は相続においてよく出てくるテーマですが…
「そもそも相続財産なの?」
「非課税枠って誰でも使えるの?」
「包括受遺者も対象なの?」
と、意外とややこしい点がたくさんあります🌀
今回は、民法と税法の考え方の違い、そして相続放棄や包括受遺者との関係性も交えながら、わかりやすく解説していきます!
🧾 保険金は相続財産?~民法と税法のズレ~
💬 民法では、生命保険金は被相続人の死亡によって発生するものの、「契約に基づき受取人が取得する財産」であるため、遺産分割の対象にはなりません。
💰 しかし税法では、「死亡を原因として取得する財産」は相続で取得したと“みなして”課税されます(=みなし相続財産)。
つまり、“相続財産じゃないのに相続税がかかる”という、ちょっと不思議な立場なのです😅
💸 非課税枠がある!でも使える人に条件あり
相続税法では、次の計算式で非課税枠が認められています。
✅ 500万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人いれば、1,500万円まで非課税枠が使えます。ただし、この“法定相続人”には注意が必要です⚠
なぜならこの法定相続人も民法と税法で考え方が違うのです…( ノД`)シクシク…
📘 民法における「法定相続人」
民法では、相続が発生したときに財産を相続する権利がある人を「法定相続人」といいます。
基本の優先順位は次のとおり👇
配偶者(常に相続人)
第一順位…子(または代襲相続人)
第二順位…親(直系尊属)
第三順位…兄弟姉妹(または代襲相続人)
💡相続放棄をすると、民法上は「最初から相続人でなかったもの」とみなされます(=権利喪失)。
💰 税法における「法定相続人」
一方、相続税法で用いられる「法定相続人の数」は、次のような目的に使われます。
相続税の基礎控除の計算
生命保険金や死亡退職金の非課税枠の計算
📌 このときの「法定相続人の数」は、相続放棄していてもカウントされます!
例:相続人が配偶者+子3人(うち1人が放棄)
→ 民法上の法定相続人の数:配偶者+子2人
→ 税法上の法定相続人の数:4人として計算(放棄者も含む)
㊟税法では養子の人数にも制限があります。
❌ 相続放棄をした人は非課税枠が「使えない」
相続放棄をしていても、非課税枠の「計算上の人数」には含まれます。しかし、放棄した本人が保険金を受け取った場合は🚫 非課税枠の適用は受けられません。
なぜなら、保険金を受け取るには、「相続人であること」が必要。
相続放棄した人は、最初から相続人でなかったと“みなされる”からです。
🧑⚖️ では、「包括受遺者」はどうなるの?
「包括受遺者」とは、遺言で「財産の全部」や「○分の○」など包括的に財産を譲り受ける人のことです。
民法では📌 包括受遺者は相続人と同じ義務を負う者であり相続人とほぼ同等の立場とされますが、非課税枠の適用がありません。(;´Д`)
つまり
相続人 … ✅ なる
相続放棄した人… ❌ ならない
包括受遺者 … ❌ ならない(相続人の立場でもあれば✅ なる)
📝 まとめ
生命保険金は、相続財産ではないのに課税対象になるという特例的な財産。そして、誰が受け取るかによって、非課税かどうかがガラッと変わります。
✅ 民法では「固有財産」
✅ 税法では「みなし相続財産」
✅ 相続人・ 相続人である包括受遺者には非課税枠がある
✅ 相続放棄者は非課税枠ナシ
💬 専門家のサポートを活用しよう!
ちょっとした判断ミスで、数百万円の相続税差が生じることもあります。相続税の専門家である税理士に相談するのが安心です😊