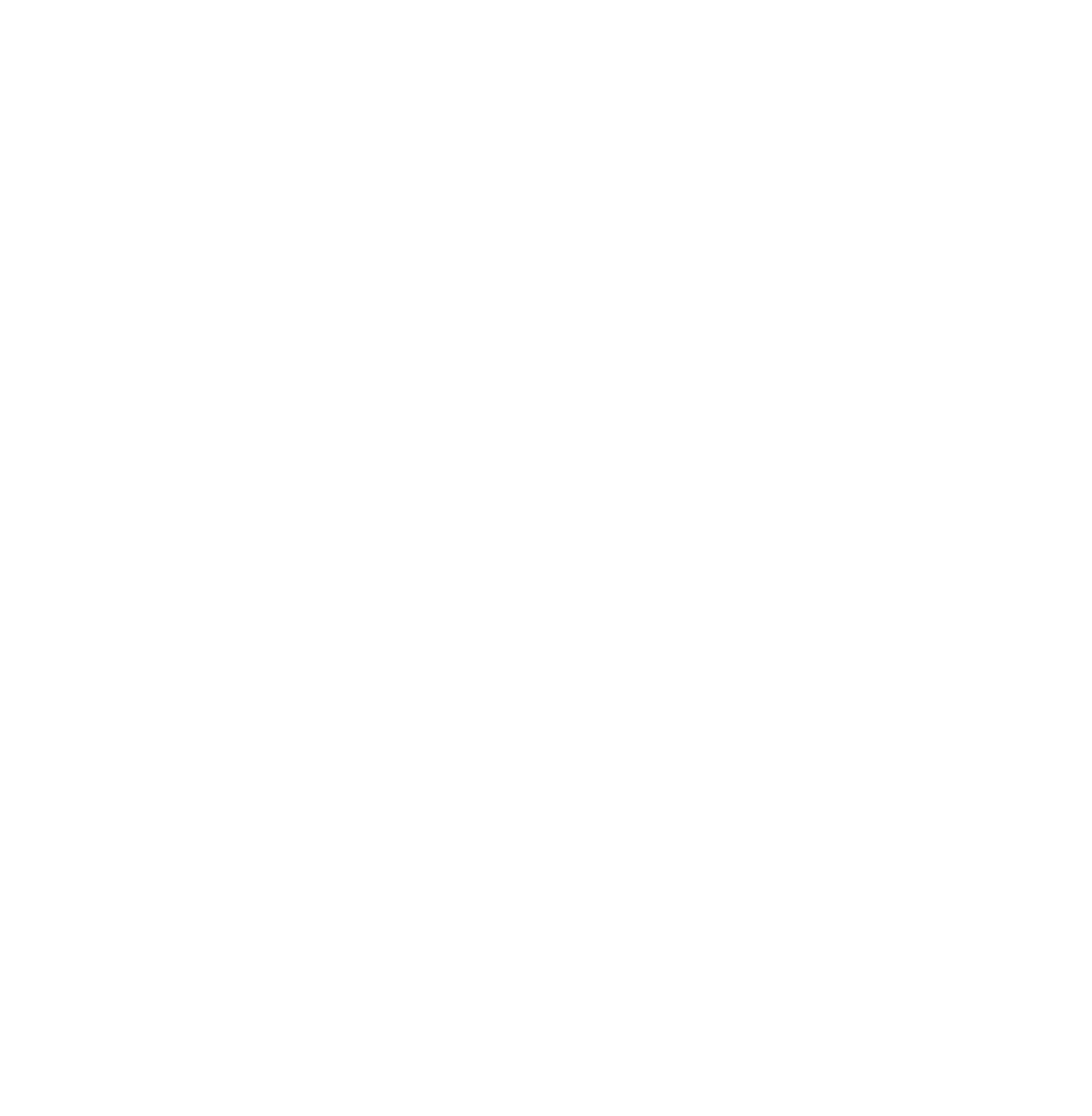ブログ
2025-05-18 13:23:41
民法891条(相続人の欠格事由)
🛑 相続できない!?相続人の「欠格事由」とは?
相続が発生すると、遺産を誰がどのくらい受け取るかが大事な問題になります。しかし中には、「相続人にはなれない人」もいます。
民法第891条では、特定の行為をした人は相続人の資格を失う(欠格事由)と定められています。
今回はそれぞれの欠格事由を、具体例でわかりやすくご紹介します(*´ω`*)
一 殺人・殺人未遂で刑に処せられた者
👴➡️💀🔪👨👦
例:
父(被相続人)を故意に殺害してしまった長男。
→ この場合、長男は刑罰を受けたことで「相続人失格」となります。
二 殺人を知って通報しなかった者
👩🦰🗣❌👮♂️(告発せず)
例:
妹が父を殺害したことを知っていた長女(直系血族でない)が、黙っていた。
→ 長女は警察に告げなかったため、相続人になれません。
※ただし「親や配偶者など」が犯人だった場合は対象外です(刑法103条(犯人蔵匿等)、104条(証拠隠滅等)は、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができるためです(;^ω^))
📘 理由1:刑法でも「親族間の犯人蔵匿や証拠隠滅」は処罰対象外
刑法第103条には、「犯人をかくまった者」は犯人蔵匿罪に問われますが、親族間ではこの罪が免除されます。(親族間不処罰の原則)。
これと同様に、告発しなかったことを相続欠格理由にするのは酷すぎると考えられています。
📘 理由2:人間の自然な感情への配慮
例えば、母親が父を殺害してしまった場合、子どもがその事実を知っていても、
「母を通報できない」
「家族が壊れてしまうのが怖い」
といった心理があるのは自然です。
このような家族感情に配慮して、民法では「配偶者や直系血族」が犯人だった場合に限って、告発しなかったことを欠格事由にしないとしています。
三 詐欺や脅迫で遺言させなかった者
例:
祖父が遺言を書こうとしたところ、法定相続人である長男が「そんなことしたら家を出ていく!」と脅してやめさせた。
→ この長男は欠格事由に該当します。
四 詐欺や脅迫で遺言を書かせた者
例:
長男が「他の子に財産をやったら恥をかかせるぞ!」と脅して父に遺言を書かせた。
→ 強制された遺言書を書かせた行為は欠格です。
五 遺言書の偽造・隠匿・破棄などをした者
例:
兄が自分に有利なように父の遺言書を書き換えたり、隠したりした。
→ 明らかな違法行為で、相続人になれません。
⚠️ 欠格事由に該当するとどうなる?
これらに該当すると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。つまり、法定相続人であっても一切相続できません。
✅ 相続欠格のポイントまとめ
①欠格の効果自体は法律上当然に発生
→ ただし、欠格者本人が争う可能性がある場合は『相続権不存在確認訴訟』などを提起して、法的に確認してもらう必要がある
②税法上も相続人とみなされない
→ 相続税の計算における「法定相続人の数」に含まれず、基礎控除や非課税枠に影響。
③代襲相続・再代襲相続は発生する
→ 欠格者の子や孫が代襲相続人として相続権を取得できる。
④二次相続には影響しない
→ 欠格は特定の被相続人との関係に限られるため、他の相続(例:母→子)では相続権を失わない。
🧑💼困ったときは専門家へ
相続には複雑な法律が関わります。
「この人は相続人として認められるの?」といった疑問がある場合は、専門家に相談しましょう(´ω´)
✅ 遺言書の有効性
✅ 欠格・排除の判断
✅ 家族間トラブルの解決
民法891条(相続人の欠格事由)
『条文内容』
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
🛑 相続できない!?相続人の「欠格事由」とは?
相続が発生すると、遺産を誰がどのくらい受け取るかが大事な問題になります。しかし中には、「相続人にはなれない人」もいます。
民法第891条では、特定の行為をした人は相続人の資格を失う(欠格事由)と定められています。
今回はそれぞれの欠格事由を、具体例でわかりやすくご紹介します(*´ω`*)
一 殺人・殺人未遂で刑に処せられた者
👴➡️💀🔪👨👦
例:
父(被相続人)を故意に殺害してしまった長男。
→ この場合、長男は刑罰を受けたことで「相続人失格」となります。
二 殺人を知って通報しなかった者
👩🦰🗣❌👮♂️(告発せず)
例:
妹が父を殺害したことを知っていた長女(直系血族でない)が、黙っていた。
→ 長女は警察に告げなかったため、相続人になれません。
※ただし「親や配偶者など」が犯人だった場合は対象外です(刑法103条(犯人蔵匿等)、104条(証拠隠滅等)は、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができるためです(;^ω^))
📘 理由1:刑法でも「親族間の犯人蔵匿や証拠隠滅」は処罰対象外
刑法第103条には、「犯人をかくまった者」は犯人蔵匿罪に問われますが、親族間ではこの罪が免除されます。(親族間不処罰の原則)。
これと同様に、告発しなかったことを相続欠格理由にするのは酷すぎると考えられています。
📘 理由2:人間の自然な感情への配慮
例えば、母親が父を殺害してしまった場合、子どもがその事実を知っていても、
「母を通報できない」
「家族が壊れてしまうのが怖い」
といった心理があるのは自然です。
このような家族感情に配慮して、民法では「配偶者や直系血族」が犯人だった場合に限って、告発しなかったことを欠格事由にしないとしています。
三 詐欺や脅迫で遺言させなかった者
例:
祖父が遺言を書こうとしたところ、法定相続人である長男が「そんなことしたら家を出ていく!」と脅してやめさせた。
→ この長男は欠格事由に該当します。
四 詐欺や脅迫で遺言を書かせた者
例:
長男が「他の子に財産をやったら恥をかかせるぞ!」と脅して父に遺言を書かせた。
→ 強制された遺言書を書かせた行為は欠格です。
五 遺言書の偽造・隠匿・破棄などをした者
例:
兄が自分に有利なように父の遺言書を書き換えたり、隠したりした。
→ 明らかな違法行為で、相続人になれません。
⚠️ 欠格事由に該当するとどうなる?
これらに該当すると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。つまり、法定相続人であっても一切相続できません。
相続税法15条2項(一部抜粋)
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
✅ 相続欠格のポイントまとめ
①欠格の効果自体は法律上当然に発生
→ ただし、欠格者本人が争う可能性がある場合は『相続権不存在確認訴訟』などを提起して、法的に確認してもらう必要がある
②税法上も相続人とみなされない
→ 相続税の計算における「法定相続人の数」に含まれず、基礎控除や非課税枠に影響。
③代襲相続・再代襲相続は発生する
→ 欠格者の子や孫が代襲相続人として相続権を取得できる。
④二次相続には影響しない
→ 欠格は特定の被相続人との関係に限られるため、他の相続(例:母→子)では相続権を失わない。
🧑💼困ったときは専門家へ
相続には複雑な法律が関わります。
「この人は相続人として認められるの?」といった疑問がある場合は、専門家に相談しましょう(´ω´)
✅ 遺言書の有効性
✅ 欠格・排除の判断
✅ 家族間トラブルの解決