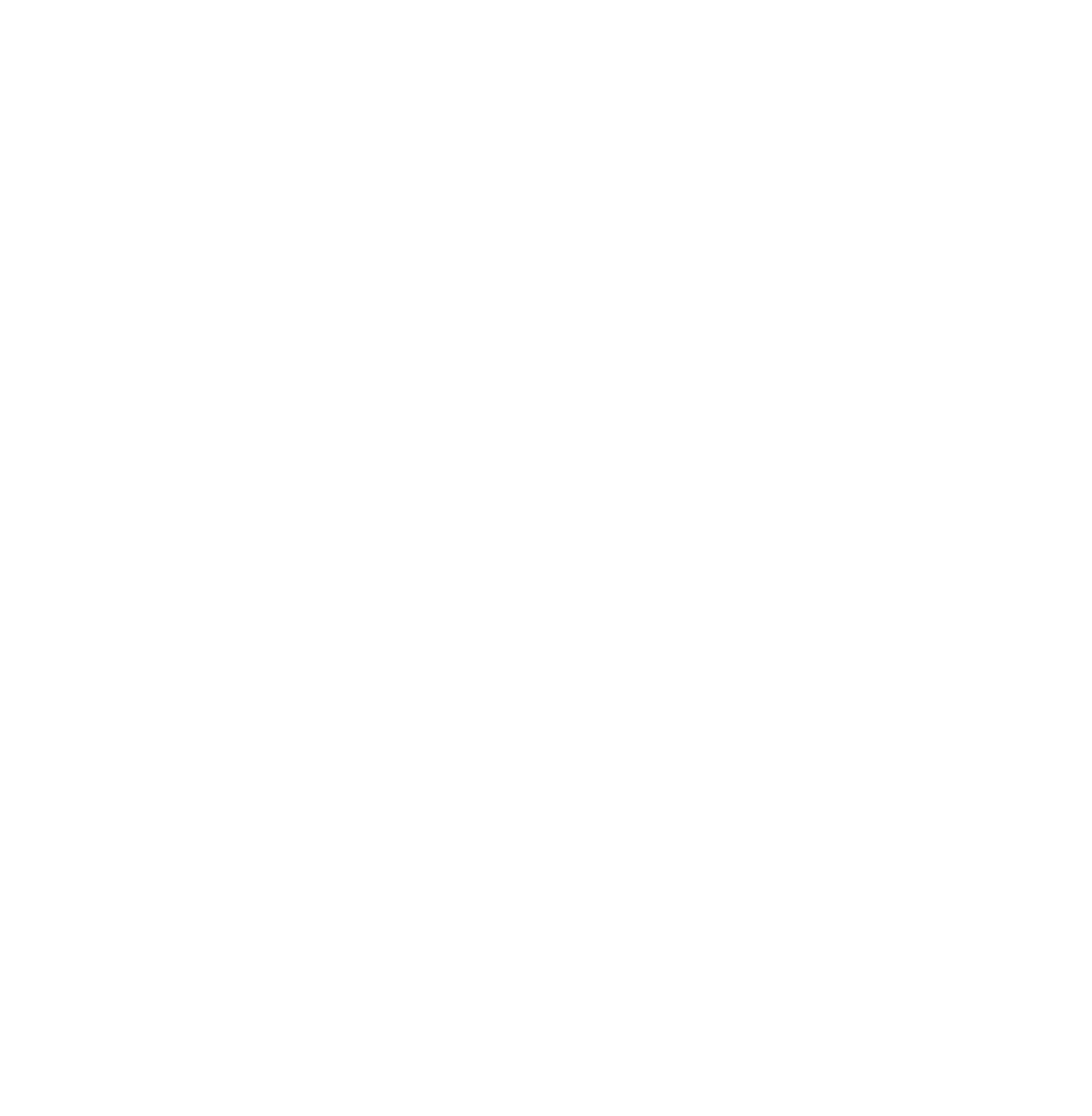ブログ
2025-05-21 12:37:58
民法893条(遺言による推定相続人の廃除)
✍️遺言で相続人を外せる?民法893条の解説🔍
遺言によって「相続人から外す」ことができる制度があるのをご存じですか?
これは【推定相続人の廃除】と呼ばれ、民法第893条で定められています。
🧑⚖️ わかりやすく言うと…
被相続人(亡くなった人)が「この人には財産を渡したくない」と考え、遺言書で明確にその意思を書いた場合には、遺言執行者が【家庭裁判所】に「廃除の手続き」を申し立てる必要があります。
💡 重要なのは、「勝手に外せるわけではない」ということ。
家庭裁判所の判断が必要です⚖️
★具体例
👴 父・太郎さんが亡くなりました。
👨 息子・一郎さんは推定相続人ですが、長年父を虐待していた過去がありました。
太郎さんは生前に、✍️「一郎を相続人から廃除する」という内容の遺言を残していました。
📄 そこで、遺言執行者が遺言に従い、家庭裁判所に廃除を申し立てたところ、
裁判所は「廃除が相当」と認め、一郎さんは相続人ではなくなりました。
🕰️ なお、廃除の効力は太郎さんが亡くなった時点にさかのぼって発生します。
❗ポイントまとめ
✅ 廃除は遺言でもできる(893条)
✅ ただし、遺言執行者が家庭裁判所に申立てする必要がある
✅ 廃除が認められると、最初から相続人でなかったことになる
㊟🧑⚖️ 被相続人が「相続させたくない」と思って遺言に書いたとしても、家庭裁判所が認めなければ廃除の効力は発生しません。また 廃除の対象は「遺留分を有する者」に限られます。(たとえば「兄弟姉妹」など、もともと遺留分がない人は、遺言で一切相続させないようにすれば十分です(´ω´)ノ)
※遺留分とは、相続人に最低限保証される相続分のこと。
つまり、特別な手続き(廃除)をしなくても、遺言だけで財産を渡さないようにできるんです。
📌 特に「感情的な不仲」や「性格の不一致」など、
客観的な証拠や法律上の理由が不十分な場合は、家庭裁判所が廃除を認めないこともあります。
🏢専門家に相談を!
相続トラブルは複雑です。
「廃除したい」「廃除されたけど納得できない」など、判断が難しい場合も多くあります。
💬 ご自身のケースに当てはまるか、必ず専門家に相談しましょう!
当事務所では、相続や遺言に関するご相談を随時受け付けております✨
📞お気軽にご相談ください📩
民法893条(遺言による推定相続人の廃除)
『条文内容』
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
✍️遺言で相続人を外せる?民法893条の解説🔍
遺言によって「相続人から外す」ことができる制度があるのをご存じですか?
これは【推定相続人の廃除】と呼ばれ、民法第893条で定められています。
🧑⚖️ わかりやすく言うと…
被相続人(亡くなった人)が「この人には財産を渡したくない」と考え、遺言書で明確にその意思を書いた場合には、遺言執行者が【家庭裁判所】に「廃除の手続き」を申し立てる必要があります。
💡 重要なのは、「勝手に外せるわけではない」ということ。
家庭裁判所の判断が必要です⚖️
★具体例
👴 父・太郎さんが亡くなりました。
👨 息子・一郎さんは推定相続人ですが、長年父を虐待していた過去がありました。
太郎さんは生前に、✍️「一郎を相続人から廃除する」という内容の遺言を残していました。
📄 そこで、遺言執行者が遺言に従い、家庭裁判所に廃除を申し立てたところ、
裁判所は「廃除が相当」と認め、一郎さんは相続人ではなくなりました。
🕰️ なお、廃除の効力は太郎さんが亡くなった時点にさかのぼって発生します。
❗ポイントまとめ
✅ 廃除は遺言でもできる(893条)
✅ ただし、遺言執行者が家庭裁判所に申立てする必要がある
✅ 廃除が認められると、最初から相続人でなかったことになる
㊟🧑⚖️ 被相続人が「相続させたくない」と思って遺言に書いたとしても、家庭裁判所が認めなければ廃除の効力は発生しません。また 廃除の対象は「遺留分を有する者」に限られます。(たとえば「兄弟姉妹」など、もともと遺留分がない人は、遺言で一切相続させないようにすれば十分です(´ω´)ノ)
※遺留分とは、相続人に最低限保証される相続分のこと。
つまり、特別な手続き(廃除)をしなくても、遺言だけで財産を渡さないようにできるんです。
📌 特に「感情的な不仲」や「性格の不一致」など、
客観的な証拠や法律上の理由が不十分な場合は、家庭裁判所が廃除を認めないこともあります。
🏢専門家に相談を!
相続トラブルは複雑です。
「廃除したい」「廃除されたけど納得できない」など、判断が難しい場合も多くあります。
💬 ご自身のケースに当てはまるか、必ず専門家に相談しましょう!
当事務所では、相続や遺言に関するご相談を随時受け付けております✨
📞お気軽にご相談ください📩