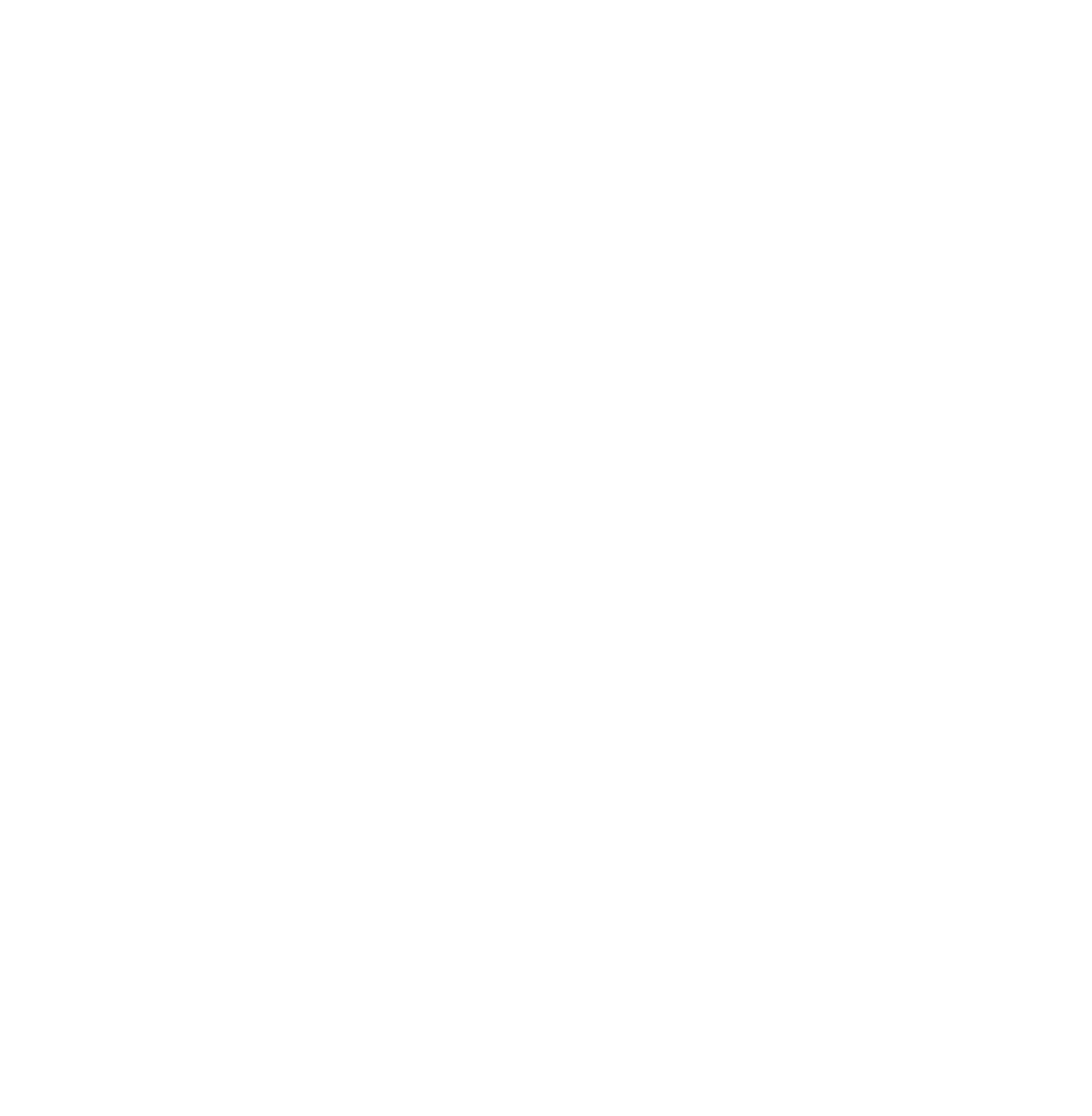ブログ
2025-05-23 10:59:04
民法895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
🧾【推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産管理】とは?
「遺産相続の場面で、推定相続人の廃除を請求していたけど、審判が確定する前に相続が始まってしまった…」
そんなとき、どうなるのでしょうか?🤔
民法第895条が、このようなケースに対応しています!
🧑⚖️民法第895条の要点をやさしく解説
📌状況
被相続人が亡くなる前に、「推定相続人の廃除」や「廃除の取消し」が家庭裁判所に請求されていた
しかし、まだ裁判所の審判(決定)は出ていない…
そんな中、被相続人が亡くなってしまい、相続が開始📅
💡このときどうなる?
家庭裁判所は、親族・利害関係人・検察官の請求により相続財産の管理について必要な処分(=管理人の選任など)を命じることができます。
つまり、
👉「誰が相続人かはまだ確定していないけど、遺産が放置されてトラブルになるのを防ぐために、一時的な管理を裁判所が指示できる」という制度です🛡️
🏠具体例:わかりやすくイメージ
👴父・太郎さん(被相続人)
👨長男・一郎さん(推定相続人、しかし虐待で廃除請求中)
👩娘・花子さん
太郎さんは生前に、一郎さんの廃除を家庭裁判所に請求していました(まだ審判は出ていない)
廃除審判の途中で太郎さんが亡くなり、相続が発生😢
すると、花子さんが家庭裁判所に「遺産を一時的に管理して欲しい」と請求💡
裁判所が遺産管理人を選任し、一郎さんに勝手に財産を動かされないように保護します🔒
⚖️条文の2項目もポイント!
家庭裁判所が遺産管理人を選ぶときは、
民法第27条〜第29条(財産管理人のルール)が準用されます📚
(財産管理人は遺産を守るための行為、価値を維持する目的の行為のみが可能でそれ以外の行為は家庭裁判所の許可が必要です)
つまり、
✅どんな人物が管理人になれるか
✅管理人の職務・責任
✅管理人の報告義務
などが法律できちんと定められています。
✅まとめ
廃除審判の確定前に相続が開始しても、遺産を安全に管理する仕組みが法律で用意されています。利害関係人や親族は、遠慮なく家庭裁判所に「必要な処分をしてほしい」と請求可能です💬
相続をめぐるトラブルを防ぐ大事な制度です!
~補足~
🧾【遺産を守る緊急措置】民法第895条の実務的な意味と使われる場面とは?
「相続人がまだ確定していない…」「遺言で廃除されてるけど裁判はまだ途中…」そんな相続の“あいまいな空白期間”に使えるルールが、民法第895条です📘
⚖️でも実務では、あまり使われない?
その通り。実際の相続の現場では…
相続人が複数いる場合、誰かが自然と保存行為(例:税金支払いや修繕)を行ったり、特にトラブルにならなければ、家庭裁判所を通さずとも現場が回るのです(;^ω^)
➡ そのため、895条を根拠に家庭裁判所へ請求がされることは少ないのが現実です。
✅ただし、使われると非常に有効な場面も!
特に注意が必要なのは、以下のようなケース👇
👤相続人が1人で、その人が「廃除請求中」または「遺言で廃除されている」場合だと、このままではその人物が遺産に手をつけるおそれがある(;´Д`A ```
一方で、廃除が確定していないから、形式的にはまだ相続人の立場にある状況Σ(゚Д゚;≡;゚д゚)
他に相続人もおらず、受遺者(第三者)も無力…
➡ このとき、民法895条に基づき家庭裁判所へ「保存措置」の請求ができる!
🔍管理人の選任までは不要な場合も?
はい。895条は「管理人の選任」だけでなく、
保存行為だけを裁判所に認めてもらうという柔軟な使い方もできます。
建物の雨漏り修繕だけを許可してもらいたい🔧
預金口座を凍結しておきたい💴
➡ 必ずしも「管理人を置く」必要はない。状況に応じて、必要最小限の措置を請求できるのが特徴です。
🧑💼相続は感情も絡む繊細な問題です。
「このケース、自分はどうしたら?」と迷ったときは、ぜひ専門家にご相談を🏢✨
当事務所では相続・廃除・遺言などのご相談を丁寧にサポートしています(´ω´)ノ
📞お気軽にお問い合わせください。
民法895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
『条文内容』
(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
🧾【推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産管理】とは?
「遺産相続の場面で、推定相続人の廃除を請求していたけど、審判が確定する前に相続が始まってしまった…」
そんなとき、どうなるのでしょうか?🤔
民法第895条が、このようなケースに対応しています!
🧑⚖️民法第895条の要点をやさしく解説
📌状況
被相続人が亡くなる前に、「推定相続人の廃除」や「廃除の取消し」が家庭裁判所に請求されていた
しかし、まだ裁判所の審判(決定)は出ていない…
そんな中、被相続人が亡くなってしまい、相続が開始📅
💡このときどうなる?
家庭裁判所は、親族・利害関係人・検察官の請求により相続財産の管理について必要な処分(=管理人の選任など)を命じることができます。
つまり、
👉「誰が相続人かはまだ確定していないけど、遺産が放置されてトラブルになるのを防ぐために、一時的な管理を裁判所が指示できる」という制度です🛡️
🏠具体例:わかりやすくイメージ
👴父・太郎さん(被相続人)
👨長男・一郎さん(推定相続人、しかし虐待で廃除請求中)
👩娘・花子さん
太郎さんは生前に、一郎さんの廃除を家庭裁判所に請求していました(まだ審判は出ていない)
廃除審判の途中で太郎さんが亡くなり、相続が発生😢
すると、花子さんが家庭裁判所に「遺産を一時的に管理して欲しい」と請求💡
裁判所が遺産管理人を選任し、一郎さんに勝手に財産を動かされないように保護します🔒
⚖️条文の2項目もポイント!
家庭裁判所が遺産管理人を選ぶときは、
民法第27条〜第29条(財産管理人のルール)が準用されます📚
(財産管理人は遺産を守るための行為、価値を維持する目的の行為のみが可能でそれ以外の行為は家庭裁判所の許可が必要です)
つまり、
✅どんな人物が管理人になれるか
✅管理人の職務・責任
✅管理人の報告義務
などが法律できちんと定められています。
✅まとめ
廃除審判の確定前に相続が開始しても、遺産を安全に管理する仕組みが法律で用意されています。利害関係人や親族は、遠慮なく家庭裁判所に「必要な処分をしてほしい」と請求可能です💬
相続をめぐるトラブルを防ぐ大事な制度です!
~補足~
🧾【遺産を守る緊急措置】民法第895条の実務的な意味と使われる場面とは?
「相続人がまだ確定していない…」「遺言で廃除されてるけど裁判はまだ途中…」そんな相続の“あいまいな空白期間”に使えるルールが、民法第895条です📘
⚖️でも実務では、あまり使われない?
その通り。実際の相続の現場では…
相続人が複数いる場合、誰かが自然と保存行為(例:税金支払いや修繕)を行ったり、特にトラブルにならなければ、家庭裁判所を通さずとも現場が回るのです(;^ω^)
➡ そのため、895条を根拠に家庭裁判所へ請求がされることは少ないのが現実です。
✅ただし、使われると非常に有効な場面も!
特に注意が必要なのは、以下のようなケース👇
👤相続人が1人で、その人が「廃除請求中」または「遺言で廃除されている」場合だと、このままではその人物が遺産に手をつけるおそれがある(;´Д`A ```
一方で、廃除が確定していないから、形式的にはまだ相続人の立場にある状況Σ(゚Д゚;≡;゚д゚)
他に相続人もおらず、受遺者(第三者)も無力…
➡ このとき、民法895条に基づき家庭裁判所へ「保存措置」の請求ができる!
🔍管理人の選任までは不要な場合も?
はい。895条は「管理人の選任」だけでなく、
保存行為だけを裁判所に認めてもらうという柔軟な使い方もできます。
建物の雨漏り修繕だけを許可してもらいたい🔧
預金口座を凍結しておきたい💴
➡ 必ずしも「管理人を置く」必要はない。状況に応じて、必要最小限の措置を請求できるのが特徴です。
🧑💼相続は感情も絡む繊細な問題です。
「このケース、自分はどうしたら?」と迷ったときは、ぜひ専門家にご相談を🏢✨
当事務所では相続・廃除・遺言などのご相談を丁寧にサポートしています(´ω´)ノ
📞お気軽にお問い合わせください。