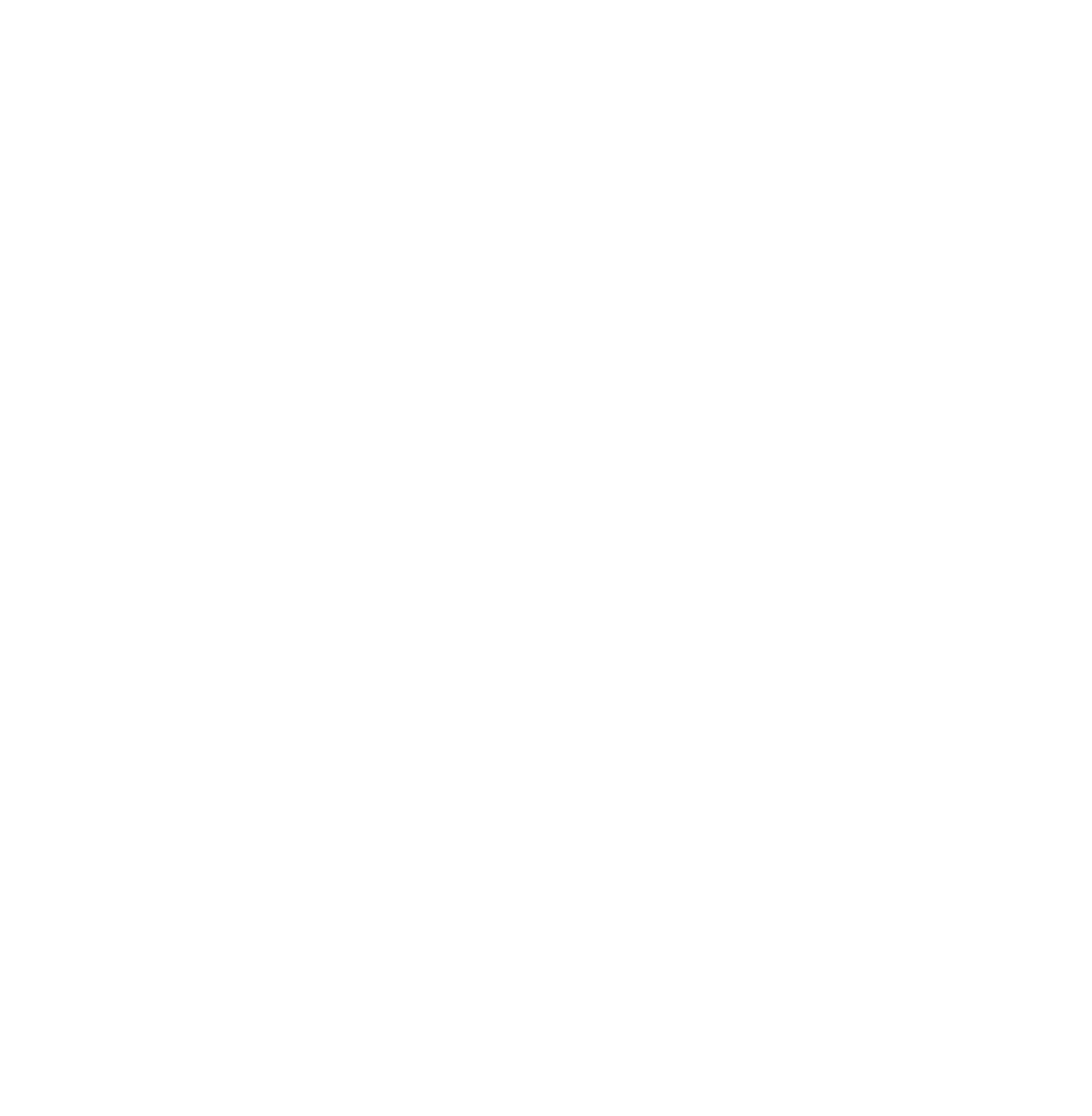ブログ
2025-05-26 20:41:41
民法897条(祭祀に関する権利の承継)
🏯 祭祀に関する権利の承継ってなに?【民法第897条の解説】
お墓や仏壇、系譜(家系図)など、家族の先祖を祀るために必要なものは、誰が引き継ぐのか❓
実はこれ、「祭祀に関する権利」として、民法でちゃんと決められているんです📜✨
「お墓・仏壇など先祖に関する大切なもの」は、通常の相続とは別枠で、 慣習や故人の意向によって決まる、ということなんです(;´・ω・)
👤 具体例①:長男が引き継ぐ家
昔から「長男が家を継ぐ」という慣習のある家では…
🧓亡くなった父の祭祀財産(お墓や仏壇など)→ 👨🦱長男が引き継ぎます。
ほかの兄弟は「相続財産」には文句を言えても、祭祀については慣習が優先されます( ノД`)シクシク…
📝 具体例②:父が遺言で指定したケース
父が遺言で「次男に祭祀を任せる」と書いていた場合…
📜遺言の指定 ✍ → 👨🦰次男が祭祀の承継者になります。
このときは慣習よりも遺言の意思が優先されますΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
⚖️ 慣習がわからないときは?
家によっては「誰がやるべきか慣習が曖昧…💦」ということもありますよね(´・ω・`)
🏛 家庭裁判所が判断します!
→ 家族間で争いになったとき、最終的には裁判所が誰が継ぐべきかを決めます(´ω´)
🙋♀️ よくあるご相談
「兄弟でもめていて、誰が祭祀をやるべきかわからない」
「長男が遠方に住んでいてお墓の管理が難しい」
「遺言があるけど、他の相続人が納得していない」
こういった場合もありますので、専門家への相談が大切です🧑💼
✅ 当事務所では「お墓の問題」もサポートできます!
お墓の承継・管理・墓じまい・永代供養など、
お墓に関する法律・手続き・実務面まで対応可能です。
ご相談例:
📝 遺言に「誰が承継するか」記載したい
🪦 墓じまいの手続きと費用の見積もりを知りたい
🤝 親族と揉めないための調整を第三者に頼みたい
📁 承継に必要な書類や手続きを一緒に進めてほしい
法律的な観点と現実的な対策をセットでご提案いたします💼✨
「誰がやるべきか分からない」「今のうちに整理したい」など、
お気軽にご相談ください。
補足(=゚ω゚)ノ
💡知っておくとも安心な専門用語
☠️ 無縁仏(むえんぼとけ)
📌 承継者や供養者がいなくなった遺骨のこと。
放置が続くと、墓地管理者により合祀されることがあります。
トラブルになる前に対策を!
💰 永代供養料(えいたいくようりょう)
📌 お寺や霊園が将来にわたって供養と管理をしてくれる費用のこと。「子どもに負担をかけたくない」という方に選ばれています。
🧾 管理料(かんりりょう)
📌 墓地・納骨堂の清掃や維持にかかる年会費。
未払いが続くと無縁仏扱いになることも⚠️
🏢 納骨堂(のうこつどう)
📌 屋内型の遺骨安置施設。
都市部では「屋内でお参りできる」「管理が楽」と人気です。
🪨 墓じまい
📌 墓石を撤去して遺骨を別の場所へ移す手続き。
費用や行政手続き(改葬許可)が必要です。
📝 改葬許可(かいそうきょか)
📌 遺骨を他所へ移す際に必要な市区町村からの許可証。
書類の不備や遅延に注意!
🧱 合祀墓(ごうしぼ)
📌 他人の遺骨と一緒に埋葬される合同のお墓。
永代供養墓の一形態で、費用が抑えられる傾向もあります。
🛕 樹木葬(じゅもくそう)
📌 自然葬の一種で、墓石の代わりに木を墓標とするスタイル。
「自然に還りたい」という思いから選ばれています。
🪦 永代供養墓
📌 寺院や霊園が責任をもって継続的に供養してくれるお墓。
承継者不要で、一定期間個別供養→合祀となるタイプもあります。
🪧 墓地使用許可証
📌 墓地の使用を認められたことを証明する大切な書類。
相続や墓じまいのときには必須書類です。
⚖️ 祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)
📌 民法第897条に基づいて、お墓・仏壇・系譜などを引き継ぐ人。
被相続人の指定があればそれが優先され、なければ慣習や家庭裁判所の判断となります。
🧑💼 祭祀財産(さいしざいさん)
📌 お墓・仏壇・位牌・系譜など、先祖をまつるための財産。
通常の相続財産とは別枠で扱われます(相続税の対象外)。
🧘♂️ 合祀(ごうし)
📌 遺骨を他の人の遺骨と一緒に埋葬すること。
無縁仏や永代供養でよく使われる方法です。
※合祀後は個別の供養や取り出しは基本的にできません。
💸 墓地返還料(ぼちへんかんりょう)
📌 墓地の契約を解消するときにかかる費用や、返還時の条件。
霊園や寺院によって異なるので事前に確認を!
民法897条(祭祀に関する権利の承継)
『条文内容』
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
🏯 祭祀に関する権利の承継ってなに?【民法第897条の解説】
お墓や仏壇、系譜(家系図)など、家族の先祖を祀るために必要なものは、誰が引き継ぐのか❓
実はこれ、「祭祀に関する権利」として、民法でちゃんと決められているんです📜✨
「お墓・仏壇など先祖に関する大切なもの」は、通常の相続とは別枠で、 慣習や故人の意向によって決まる、ということなんです(;´・ω・)
👤 具体例①:長男が引き継ぐ家
昔から「長男が家を継ぐ」という慣習のある家では…
🧓亡くなった父の祭祀財産(お墓や仏壇など)→ 👨🦱長男が引き継ぎます。
ほかの兄弟は「相続財産」には文句を言えても、祭祀については慣習が優先されます( ノД`)シクシク…
📝 具体例②:父が遺言で指定したケース
父が遺言で「次男に祭祀を任せる」と書いていた場合…
📜遺言の指定 ✍ → 👨🦰次男が祭祀の承継者になります。
このときは慣習よりも遺言の意思が優先されますΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
⚖️ 慣習がわからないときは?
家によっては「誰がやるべきか慣習が曖昧…💦」ということもありますよね(´・ω・`)
🏛 家庭裁判所が判断します!
→ 家族間で争いになったとき、最終的には裁判所が誰が継ぐべきかを決めます(´ω´)
🙋♀️ よくあるご相談
「兄弟でもめていて、誰が祭祀をやるべきかわからない」
「長男が遠方に住んでいてお墓の管理が難しい」
「遺言があるけど、他の相続人が納得していない」
こういった場合もありますので、専門家への相談が大切です🧑💼
✅ 当事務所では「お墓の問題」もサポートできます!
お墓の承継・管理・墓じまい・永代供養など、
お墓に関する法律・手続き・実務面まで対応可能です。
ご相談例:
📝 遺言に「誰が承継するか」記載したい
🪦 墓じまいの手続きと費用の見積もりを知りたい
🤝 親族と揉めないための調整を第三者に頼みたい
📁 承継に必要な書類や手続きを一緒に進めてほしい
法律的な観点と現実的な対策をセットでご提案いたします💼✨
「誰がやるべきか分からない」「今のうちに整理したい」など、
お気軽にご相談ください。
補足(=゚ω゚)ノ
💡知っておくとも安心な専門用語
☠️ 無縁仏(むえんぼとけ)
📌 承継者や供養者がいなくなった遺骨のこと。
放置が続くと、墓地管理者により合祀されることがあります。
トラブルになる前に対策を!
💰 永代供養料(えいたいくようりょう)
📌 お寺や霊園が将来にわたって供養と管理をしてくれる費用のこと。「子どもに負担をかけたくない」という方に選ばれています。
🧾 管理料(かんりりょう)
📌 墓地・納骨堂の清掃や維持にかかる年会費。
未払いが続くと無縁仏扱いになることも⚠️
🏢 納骨堂(のうこつどう)
📌 屋内型の遺骨安置施設。
都市部では「屋内でお参りできる」「管理が楽」と人気です。
🪨 墓じまい
📌 墓石を撤去して遺骨を別の場所へ移す手続き。
費用や行政手続き(改葬許可)が必要です。
📝 改葬許可(かいそうきょか)
📌 遺骨を他所へ移す際に必要な市区町村からの許可証。
書類の不備や遅延に注意!
🧱 合祀墓(ごうしぼ)
📌 他人の遺骨と一緒に埋葬される合同のお墓。
永代供養墓の一形態で、費用が抑えられる傾向もあります。
🛕 樹木葬(じゅもくそう)
📌 自然葬の一種で、墓石の代わりに木を墓標とするスタイル。
「自然に還りたい」という思いから選ばれています。
🪦 永代供養墓
📌 寺院や霊園が責任をもって継続的に供養してくれるお墓。
承継者不要で、一定期間個別供養→合祀となるタイプもあります。
🪧 墓地使用許可証
📌 墓地の使用を認められたことを証明する大切な書類。
相続や墓じまいのときには必須書類です。
⚖️ 祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)
📌 民法第897条に基づいて、お墓・仏壇・系譜などを引き継ぐ人。
被相続人の指定があればそれが優先され、なければ慣習や家庭裁判所の判断となります。
🧑💼 祭祀財産(さいしざいさん)
📌 お墓・仏壇・位牌・系譜など、先祖をまつるための財産。
通常の相続財産とは別枠で扱われます(相続税の対象外)。
🧘♂️ 合祀(ごうし)
📌 遺骨を他の人の遺骨と一緒に埋葬すること。
無縁仏や永代供養でよく使われる方法です。
※合祀後は個別の供養や取り出しは基本的にできません。
💸 墓地返還料(ぼちへんかんりょう)
📌 墓地の契約を解消するときにかかる費用や、返還時の条件。
霊園や寺院によって異なるので事前に確認を!