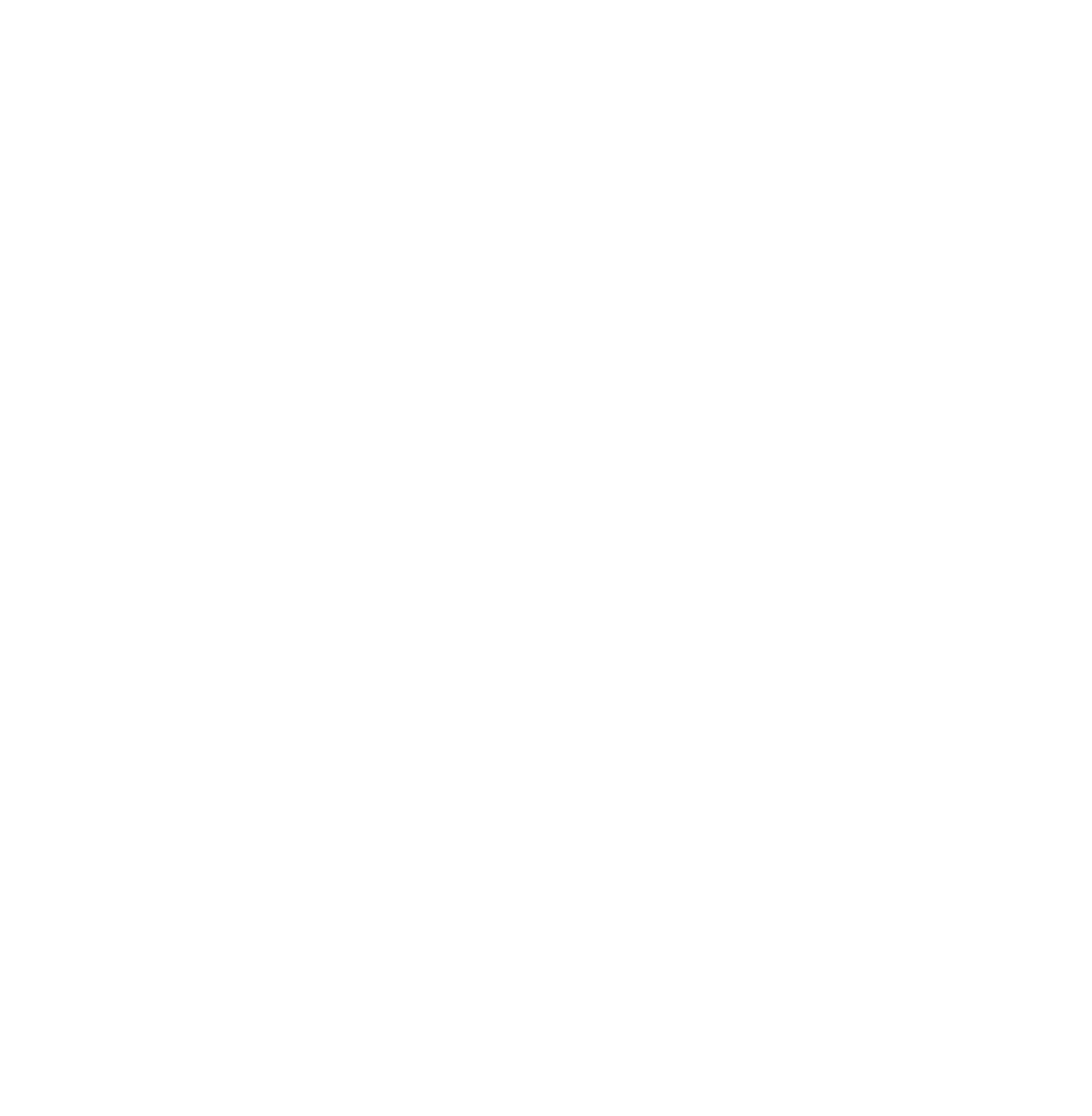ブログ
2025-05-27 17:40:52
民法897条(相続財産の保存)
🏠【相続財産の保存】って何?管理人選任の具体例付きでやさしく解説!
相続手続き中、「財産を誰がどう管理するの?」という疑問を持ったことはありませんか?
そんなときに関係してくるのが、民法第897条の2「相続財産の保存」というルールです📜
今回はこの条文について、具体例とともにわかりやすく説明します😊
🔍条文のポイント(民法897条の2)
家庭裁判所は、利害関係人(相続人、債権者、遺言受遺者など)や検察官の請求により、
✅ 相続財産の管理人の選任
✅ 相続財産を守るための必要な措置
を命じることができます。
ただし、以下の場合は例外です❌
相続人が1人で、すでに単純承認している場合
相続人全員で遺産分割が終わっている場合
相続財産清算人がすでに選任されている場合(民法952条)
💡具体例で理解しよう!
✅ 例1:相続人がもめていて財産が放置されている場合
👨⚖️父が亡くなり、相続人はAさん、Bさん、Cさんの3人。
しかし、誰も遺産分割を進めず、父の不動産が無人で管理されないまま放置…。
➡️ このままだと資産価値が下がったり、近所に迷惑をかけたりします。
📩 この場合、近隣住民や利害関係者が家庭裁判所に「相続財産管理人の選任」を申立てることができます。
✅ 例2:借金の返済を求める債権者が請求するケース
💰被相続人には多額の借金がありました。
債権者としては「財産が勝手に処分されないか不安…」。
➡️ そこで債権者は家庭裁判所に「財産の保存」を求め、管理人を選んでもらうことで、財産の勝手な散逸を防げます👮♂️
✅ 例3:相続人が未確定で、誰も手続きを進めない
👤亡くなった方に身寄りがなく、相続人が不明…。
➡️ このような場合、検察官が家庭裁判所に申し立てて、管理人を選任し、相続財産を保存します。
🧾 補足:選任された「相続財産管理人」って?
管理人が選ばれると、次のようなことができます:
①相続財産の調査・把握
②価値を保つための維持管理(例:空き家の修繕や管理)
③必要な支出(税金・保険料など)の支払い
📘このとき、民法27条〜29条の「不在者財産管理人」に関するルールが準用されます。
💰【報酬はどれくらい?】相続財産管理人の報酬の目安
相続財産管理人は専門職(弁護士・司法書士など)が選ばれることが多く、報酬は財産の内容や業務の量に応じて家庭裁判所が決定します。
📊報酬の一例(目安)
預金100万円程度…5〜10万円程度
不動産あり・債権者対応あり…20〜50万円以上
大規模な財産・複雑なケース…100万円以上になることも
📌報酬は基本的に相続財産の中から支払われます。
💸【相続財産に現金がない場合は?】
ここがポイントです👇
✅ケース1:不動産しかない場合
相続財産が土地や建物だけで現金がない場合、家庭裁判所が管理人に対して「不動産の売却許可」を出すことがあります。
➡️ 売却して得たお金から報酬や諸費用を支払う流れです。
✅ケース2:全く資産がない場合(ゼロに近い)
申立人(相続人や債権者など)が報酬や実費を立替える必要があります。
相続財産から支払えないことが明らかであれば、家庭裁判所が選任を見送ることもあります。
✅ケース3:立替費用も出せない…
この場合、相続人が相続放棄を検討するか、債権者が法的に費用をかける意味があるかどうかを見極める必要があります。
「相続財産管理人」の具体的な流れは国交省のHP参照
🌸まとめ
相続は「誰がもらうか」だけでなく、「それまでどう守るか」も大切です🛡️
相続財産が放置されるとトラブルの元。困ったら、家庭裁判所に「管理人選任」の申し立てを検討してみてください。
📩相続の実務や申立書の作成が必要な方は、当事務所までお気軽にご相談ください!
司法書士・税理士・行政書士など、ワンストップでサポートします✨
民法897条(相続財産の保存)
『条文内容』
(相続財産の保存)
第八百九十七条の二 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
(相続財産の保存)
第八百九十七条の二 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
🏠【相続財産の保存】って何?管理人選任の具体例付きでやさしく解説!
相続手続き中、「財産を誰がどう管理するの?」という疑問を持ったことはありませんか?
そんなときに関係してくるのが、民法第897条の2「相続財産の保存」というルールです📜
今回はこの条文について、具体例とともにわかりやすく説明します😊
🔍条文のポイント(民法897条の2)
家庭裁判所は、利害関係人(相続人、債権者、遺言受遺者など)や検察官の請求により、
✅ 相続財産の管理人の選任
✅ 相続財産を守るための必要な措置
を命じることができます。
ただし、以下の場合は例外です❌
相続人が1人で、すでに単純承認している場合
相続人全員で遺産分割が終わっている場合
相続財産清算人がすでに選任されている場合(民法952条)
💡具体例で理解しよう!
✅ 例1:相続人がもめていて財産が放置されている場合
👨⚖️父が亡くなり、相続人はAさん、Bさん、Cさんの3人。
しかし、誰も遺産分割を進めず、父の不動産が無人で管理されないまま放置…。
➡️ このままだと資産価値が下がったり、近所に迷惑をかけたりします。
📩 この場合、近隣住民や利害関係者が家庭裁判所に「相続財産管理人の選任」を申立てることができます。
✅ 例2:借金の返済を求める債権者が請求するケース
💰被相続人には多額の借金がありました。
債権者としては「財産が勝手に処分されないか不安…」。
➡️ そこで債権者は家庭裁判所に「財産の保存」を求め、管理人を選んでもらうことで、財産の勝手な散逸を防げます👮♂️
✅ 例3:相続人が未確定で、誰も手続きを進めない
👤亡くなった方に身寄りがなく、相続人が不明…。
➡️ このような場合、検察官が家庭裁判所に申し立てて、管理人を選任し、相続財産を保存します。
🧾 補足:選任された「相続財産管理人」って?
管理人が選ばれると、次のようなことができます:
①相続財産の調査・把握
②価値を保つための維持管理(例:空き家の修繕や管理)
③必要な支出(税金・保険料など)の支払い
📘このとき、民法27条〜29条の「不在者財産管理人」に関するルールが準用されます。
💰【報酬はどれくらい?】相続財産管理人の報酬の目安
相続財産管理人は専門職(弁護士・司法書士など)が選ばれることが多く、報酬は財産の内容や業務の量に応じて家庭裁判所が決定します。
📊報酬の一例(目安)
預金100万円程度…5〜10万円程度
不動産あり・債権者対応あり…20〜50万円以上
大規模な財産・複雑なケース…100万円以上になることも
📌報酬は基本的に相続財産の中から支払われます。
💸【相続財産に現金がない場合は?】
ここがポイントです👇
✅ケース1:不動産しかない場合
相続財産が土地や建物だけで現金がない場合、家庭裁判所が管理人に対して「不動産の売却許可」を出すことがあります。
➡️ 売却して得たお金から報酬や諸費用を支払う流れです。
✅ケース2:全く資産がない場合(ゼロに近い)
申立人(相続人や債権者など)が報酬や実費を立替える必要があります。
相続財産から支払えないことが明らかであれば、家庭裁判所が選任を見送ることもあります。
✅ケース3:立替費用も出せない…
この場合、相続人が相続放棄を検討するか、債権者が法的に費用をかける意味があるかどうかを見極める必要があります。
「相続財産管理人」の具体的な流れは国交省のHP参照
🌸まとめ
相続は「誰がもらうか」だけでなく、「それまでどう守るか」も大切です🛡️
相続財産が放置されるとトラブルの元。困ったら、家庭裁判所に「管理人選任」の申し立てを検討してみてください。
📩相続の実務や申立書の作成が必要な方は、当事務所までお気軽にご相談ください!
司法書士・税理士・行政書士など、ワンストップでサポートします✨