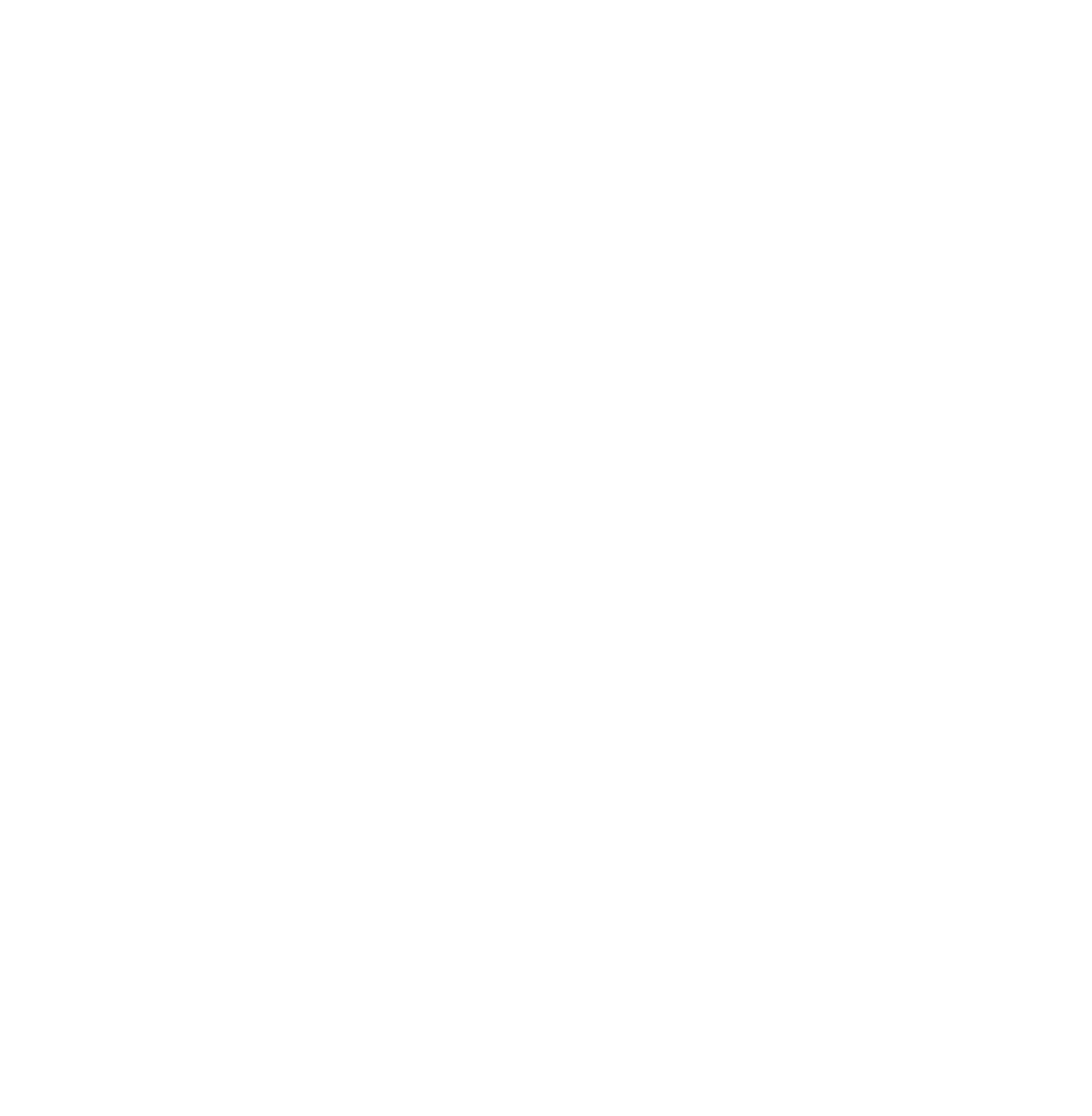ブログ
2025-05-29 09:26:19
民法898条(共同相続の効力)
🏠共同相続の効力ってなに?〜相続財産はみんなのもの〜
こんにちは!今回は【民法第898条】に定められた「共同相続の効力」について、できるだけわかりやすく解説します✨
相続が発生したとき、すぐに「誰のもの」と決まるのではなく、相続人全員の共有財産(=みんなのもの)になる、という仕組みです!(;´Д`)
🧑⚖️具体例で見てみましょう!
🧓父Aさんが亡くなり、相続人は…
👩🦱長女Bさん
👨🦱長男Cさん
👩🦳配偶者Dさん(妻)
父Aさんの遺産は以下の通り:
🏡 自宅(不動産):2,000万円
💰 預貯金:1,000万円
🧮まずは「法定相続分」で計算
法定相続分は以下のとおり👇
(配偶者と子ども2人の場合)
👩🦱長女Bさん…1/4
👨🦱長男Cさん…1/4
👩🦳配偶者Dさん(妻)…1/2
この割合がそのまま「共有持分」となります。
📌注意ポイント:
この時点では、不動産の所有権は「3人で共有」しており、誰か1人の単独名義にはなっていません。
⚠️まだ「分け終わって」いない!
✅ この「共有」状態は遺産分割協議で財産を具体的に分けるまで続きます。
📝 例えば妻Dが自宅を単独で相続し、子どもたちは預貯金を分けるなどと話し合って合意すれば、それぞれの名義に登記や口座変更をできます。
🧠まとめ
✔ 相続が始まった瞬間、財産は「共有」に
✔ 各人の持分は法定相続分に基づく
✔ 実際の名義変更は「遺産分割協議」が必要
💡補足:勝手に使っていいの?
共有状態では、勝手に不動産を売却したり貸したりすることはできません!
共有者全員の同意が必要になります⚠️
📘 民法第898条は、「相続人全員で遺産を分け合うまでのルール」を定めた大事な条文です。
遺産分割でトラブルにならないためにも、共有の考え方を知っておきましょう!
🏡遺産分割前でも相続登記は単独でできる?
~「保存行為」としての登記とその落とし穴~
🔹よくある誤解:「遺産分割してからでないと登記できない?」
「遺産分割協議が終わるまでは、名義変更(登記)はできない」と思われている方も多いのですが…
📝実は、できるケースがあります!
それが、「保存行為としての相続登記」です。
💡登記は“保存行為”にあたる
🔍保存行為とは?
民法第252条に定める「共有物に関する保存行為」とは、「物の現状維持のために必要な行為」であり、共有者の一人だけでも単独で行えるとされています。
つまり相続財産(不動産)を法的に保全するための登記は、他の相続人の同意がなくても行えるのです。
🧑⚖️具体例:法定相続分での登記
👵母が亡くなり、子ども2人(長男・長女)が相続人。
遺産分割協議がまだまとまっていないが、不動産がある。
長男が、自分の法定相続分(例えば1/2)での登記を先に行った。
✅これは問題ありません。
✅他の相続人の署名・実印も不要です。
✅法務局でも受理されます。
📌なぜこんな制度があるの?
不動産が他人に勝手に売られたり、差押えされたりするのを防ぐためです。
たとえば名義変更がなされていないと、第三者に登記されるリスクがある(;´Д`)
時間が経つと、共有者の死亡や相続が重なり相続関係が複雑化してしまうΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
➡️こうしたトラブルを回避するために、早期の登記(保存行為)を認めているのです。
⚠️注意!保存行為=所有確定ではない
ここが最大の落とし穴です。
🧠法定相続分での登記 ≠ 所有権が確定したわけではない!
その後の遺産分割協議で「他の相続人がその不動産を取得する」となれば、再度登記のやり直し(持分移転登記)が必要になります。
🌀想定される弊害
遺産分割協議をせずに登記したことで他の相続人との関係悪化
→「勝手に登記した!」と誤解されることも
分割後に再度登記の手続きが必要となる
→ 登録免許税・司法書士報酬が2重にかかるケースも
持分を売却されるリスク(理論上)
→ 登記名義ができると、持分のみ第三者に売却も可能
📘まとめ
遺産分割が終わっていなくても、法定相続分での登記は可能ですがこれは「保存行為」であり、他の相続人の同意は不要です(´ω´)ノただし、あくまで相続権の「仮の姿」であり、後で変更の可能性ありますので、実務では、他の相続人と一言相談してから登記するのがトラブル回避のコツとなります🗣️ただ、実際は相続の保存登記はあまり見かけないのでやはり遺産分割協議を経て行うのが無難化と思います(;^ω^)
民法898条(共同相続の効力)
『条文内容』
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
🏠共同相続の効力ってなに?〜相続財産はみんなのもの〜
こんにちは!今回は【民法第898条】に定められた「共同相続の効力」について、できるだけわかりやすく解説します✨
相続が発生したとき、すぐに「誰のもの」と決まるのではなく、相続人全員の共有財産(=みんなのもの)になる、という仕組みです!(;´Д`)
🧑⚖️具体例で見てみましょう!
🧓父Aさんが亡くなり、相続人は…
👩🦱長女Bさん
👨🦱長男Cさん
👩🦳配偶者Dさん(妻)
父Aさんの遺産は以下の通り:
🏡 自宅(不動産):2,000万円
💰 預貯金:1,000万円
🧮まずは「法定相続分」で計算
法定相続分は以下のとおり👇
(配偶者と子ども2人の場合)
👩🦱長女Bさん…1/4
👨🦱長男Cさん…1/4
👩🦳配偶者Dさん(妻)…1/2
この割合がそのまま「共有持分」となります。
📌注意ポイント:
この時点では、不動産の所有権は「3人で共有」しており、誰か1人の単独名義にはなっていません。
⚠️まだ「分け終わって」いない!
✅ この「共有」状態は遺産分割協議で財産を具体的に分けるまで続きます。
📝 例えば妻Dが自宅を単独で相続し、子どもたちは預貯金を分けるなどと話し合って合意すれば、それぞれの名義に登記や口座変更をできます。
🧠まとめ
✔ 相続が始まった瞬間、財産は「共有」に
✔ 各人の持分は法定相続分に基づく
✔ 実際の名義変更は「遺産分割協議」が必要
💡補足:勝手に使っていいの?
共有状態では、勝手に不動産を売却したり貸したりすることはできません!
共有者全員の同意が必要になります⚠️
📘 民法第898条は、「相続人全員で遺産を分け合うまでのルール」を定めた大事な条文です。
遺産分割でトラブルにならないためにも、共有の考え方を知っておきましょう!
🏡遺産分割前でも相続登記は単独でできる?
~「保存行為」としての登記とその落とし穴~
🔹よくある誤解:「遺産分割してからでないと登記できない?」
「遺産分割協議が終わるまでは、名義変更(登記)はできない」と思われている方も多いのですが…
📝実は、できるケースがあります!
それが、「保存行為としての相続登記」です。
💡登記は“保存行為”にあたる
🔍保存行為とは?
民法第252条に定める「共有物に関する保存行為」とは、「物の現状維持のために必要な行為」であり、共有者の一人だけでも単独で行えるとされています。
つまり相続財産(不動産)を法的に保全するための登記は、他の相続人の同意がなくても行えるのです。
🧑⚖️具体例:法定相続分での登記
👵母が亡くなり、子ども2人(長男・長女)が相続人。
遺産分割協議がまだまとまっていないが、不動産がある。
長男が、自分の法定相続分(例えば1/2)での登記を先に行った。
✅これは問題ありません。
✅他の相続人の署名・実印も不要です。
✅法務局でも受理されます。
📌なぜこんな制度があるの?
不動産が他人に勝手に売られたり、差押えされたりするのを防ぐためです。
たとえば名義変更がなされていないと、第三者に登記されるリスクがある(;´Д`)
時間が経つと、共有者の死亡や相続が重なり相続関係が複雑化してしまうΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
➡️こうしたトラブルを回避するために、早期の登記(保存行為)を認めているのです。
⚠️注意!保存行為=所有確定ではない
ここが最大の落とし穴です。
🧠法定相続分での登記 ≠ 所有権が確定したわけではない!
その後の遺産分割協議で「他の相続人がその不動産を取得する」となれば、再度登記のやり直し(持分移転登記)が必要になります。
🌀想定される弊害
遺産分割協議をせずに登記したことで他の相続人との関係悪化
→「勝手に登記した!」と誤解されることも
分割後に再度登記の手続きが必要となる
→ 登録免許税・司法書士報酬が2重にかかるケースも
持分を売却されるリスク(理論上)
→ 登記名義ができると、持分のみ第三者に売却も可能
📘まとめ
遺産分割が終わっていなくても、法定相続分での登記は可能ですがこれは「保存行為」であり、他の相続人の同意は不要です(´ω´)ノただし、あくまで相続権の「仮の姿」であり、後で変更の可能性ありますので、実務では、他の相続人と一言相談してから登記するのがトラブル回避のコツとなります🗣️ただ、実際は相続の保存登記はあまり見かけないのでやはり遺産分割協議を経て行うのが無難化と思います(;^ω^)