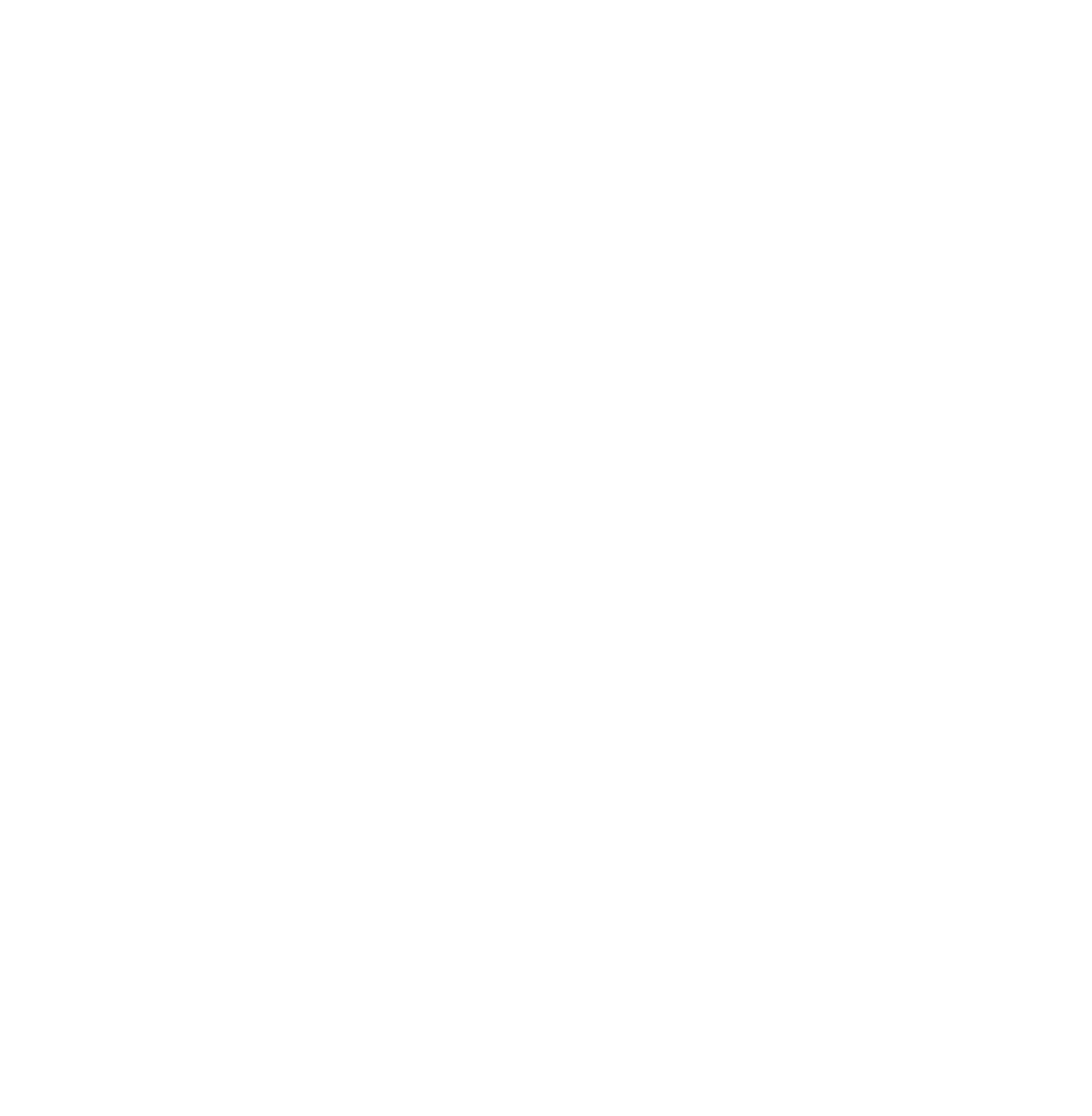ブログ
2025-06-09 09:48:16
民法902条(遺言による相続分の指定)
✍️遺言で相続分を自由に決められるってホント?【民法第902条】
相続は基本的に民法のルール(法定相続分)で分けるのが原則ですが…実は、被相続人(亡くなった方)の 遺言ひとつで、このルールを変えることができるのです❗
「相続分の指定」とは?
📜 民法第902条では、被相続人は次のことができます(´ω´)ノ
💡 相続人ごとに自由な割合で相続分を指定できる
💡 誰に何割という指定を、第三者(例:信頼できる専門家)に任せることも可能
🧩 相続分の指定と包括遺贈の違い
相続分を「割合」で与えるという点では似ている「包括遺贈」と混同されがちです。
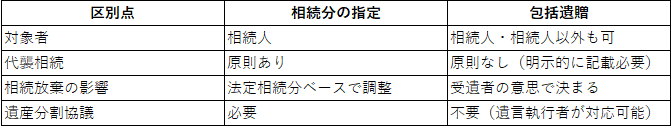
🧠 判断が難しいケースでは、文言の違いで解釈が180度変わることも。専門家の確認が重要です!
⚠️ よくある注意点と問題点
割合の合計が100%になっていない(;´・ω・)
→ 遺言が不完全と解され、解釈や補完が必要になります。
相続人が漏れている(;´∀´)
→ 指定のない相続人がトラブルの原因に。
遺留分との関係( ノД`)シクシク…
→ 「ゼロ」と指定された相続人が遺留分侵害額請求をする可能性あり。
第三者指定の曖昧性(。´・ω・)?
→ 誰がどう決めるのか不明確なケースも。
遺言執行者による実行ができない(´・ω・`)
→ 相続分の指定だけでは執行者が動けないため、結局遺産分割協議が必要。
🧠 トラブル防止のために:専門家の関与がカギ!
遺言による相続分の指定は、確かに強力な手段ですが、表現や記載方法次第で解釈が分かれる危険性があります。
✅ 専門家に相談することで得られるメリット(*´ω`*)
①正確な文言による遺言作成
②将来的な遺留分請求や無効主張のリスク回避
③相続人間のトラブル防止
④税務的な最適化による節税効果
結論:意思を確実に実現するために
遺言による「相続分の指定」は、法定相続ルールに縛られず、被相続人の想いをダイレクトに反映できる優れた制度です。
しかし、その運用には注意点も多く、内容次第ではかえって相続人間の紛争を引き起こしかねません。
💬「どう書けばよいか分からない」
💬「相続人の関係が複雑で…」
そんな方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。相続実務に精通した専門家が、あなたの意思を法的に確実に実現するお手伝いをいたします(´ω´)ノ
民法902条(遺言による相続分の指定)
『条文内容』
(遺言による相続分の指定)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
(遺言による相続分の指定)
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
✍️遺言で相続分を自由に決められるってホント?【民法第902条】
相続は基本的に民法のルール(法定相続分)で分けるのが原則ですが…実は、被相続人(亡くなった方)の 遺言ひとつで、このルールを変えることができるのです❗
「相続分の指定」とは?
📜 民法第902条では、被相続人は次のことができます(´ω´)ノ
💡 相続人ごとに自由な割合で相続分を指定できる
💡 誰に何割という指定を、第三者(例:信頼できる専門家)に任せることも可能
🧩 相続分の指定と包括遺贈の違い
相続分を「割合」で与えるという点では似ている「包括遺贈」と混同されがちです。
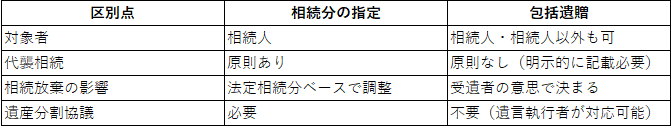
🧠 判断が難しいケースでは、文言の違いで解釈が180度変わることも。専門家の確認が重要です!
⚠️ よくある注意点と問題点
割合の合計が100%になっていない(;´・ω・)
→ 遺言が不完全と解され、解釈や補完が必要になります。
相続人が漏れている(;´∀´)
→ 指定のない相続人がトラブルの原因に。
遺留分との関係( ノД`)シクシク…
→ 「ゼロ」と指定された相続人が遺留分侵害額請求をする可能性あり。
第三者指定の曖昧性(。´・ω・)?
→ 誰がどう決めるのか不明確なケースも。
遺言執行者による実行ができない(´・ω・`)
→ 相続分の指定だけでは執行者が動けないため、結局遺産分割協議が必要。
🧠 トラブル防止のために:専門家の関与がカギ!
遺言による相続分の指定は、確かに強力な手段ですが、表現や記載方法次第で解釈が分かれる危険性があります。
✅ 専門家に相談することで得られるメリット(*´ω`*)
①正確な文言による遺言作成
②将来的な遺留分請求や無効主張のリスク回避
③相続人間のトラブル防止
④税務的な最適化による節税効果
結論:意思を確実に実現するために
遺言による「相続分の指定」は、法定相続ルールに縛られず、被相続人の想いをダイレクトに反映できる優れた制度です。
しかし、その運用には注意点も多く、内容次第ではかえって相続人間の紛争を引き起こしかねません。
💬「どう書けばよいか分からない」
💬「相続人の関係が複雑で…」
そんな方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。相続実務に精通した専門家が、あなたの意思を法的に確実に実現するお手伝いをいたします(´ω´)ノ