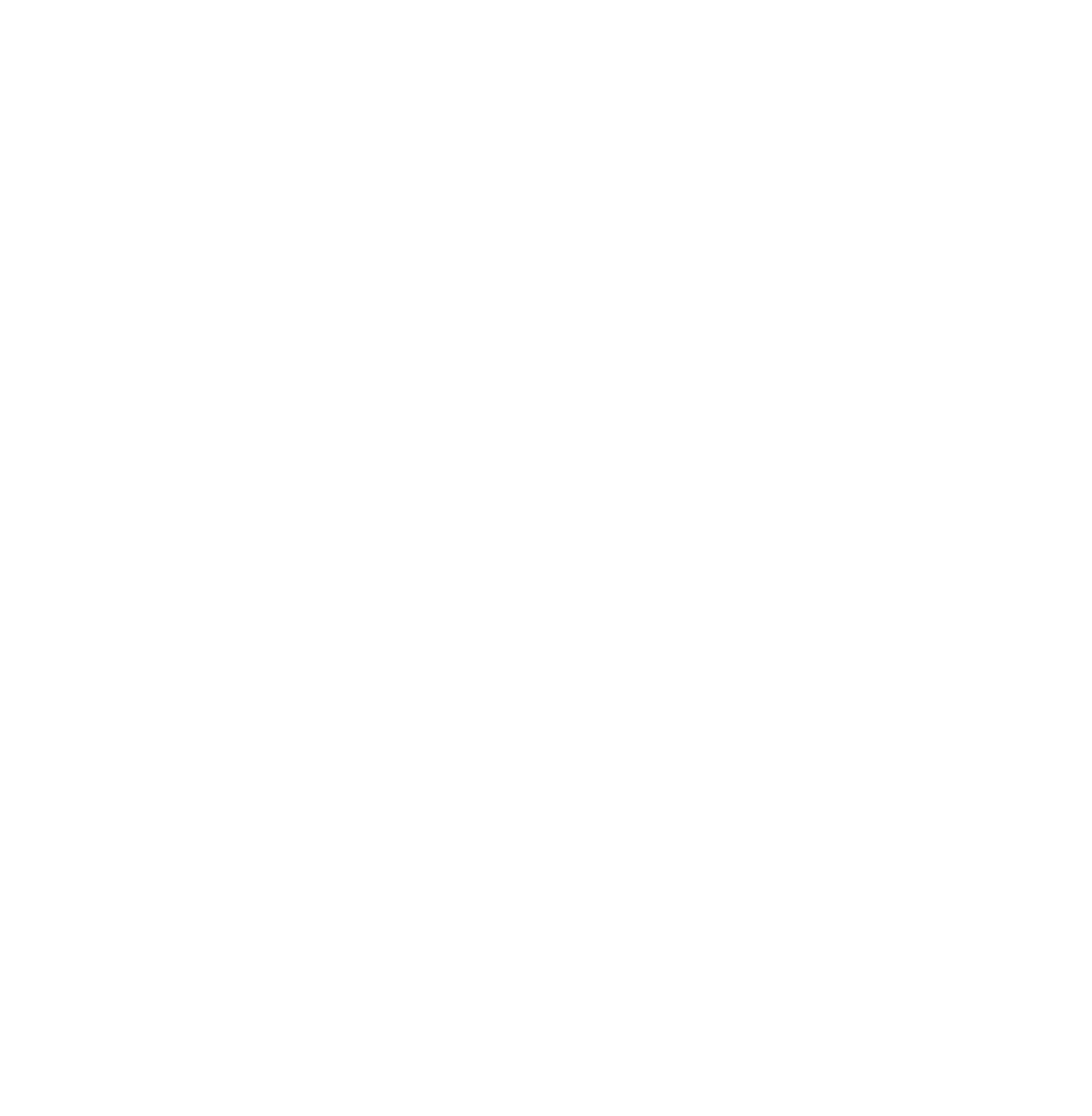ブログ
2025-06-11 10:47:49
民法903条(特別受益者の相続分)
🏠特別受益とは?相続分が変わるってホント?
こんにちは(´ω´)ノ
今回は、相続でもめやすい「特別受益」について、民法903条をもとにわかりやすく解説します✨
親から結婚資金や住宅購入資金の援助を受けたことがある方は…
👉 相続時に損する可能性があるかも!?Σ(゚Д゚;≡;゚д゚)
🧑⚖️民法903条とは?
被相続人(亡くなった方)から特別な贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、その相続人はその分を相続分から差し引かれるルールがあります。これを「特別受益の持ち戻し」といいます📘
💡具体例でスッキリ理解!
🏡登場人物
👴 父(被相続人)
👦 長男A:住宅購入時に1,000万円の援助を受けた
👧 長女B:特別な援助なし
🪙父の遺産総額:3,000万円
長男Aが過去に受けた1,000万円の援助は「特別受益」とみなされます(;´Д`)
🧮計算方法
持ち戻し財産=相続財産3,000万円+特別受益1,000万円=4,000万円
法定相続分(子が2人)=各2,000万円(4,000万円 ÷ 2)
長男Aの取り分=2,000万円-1,000万円(特別受益)=1,000万円
長女Bの取り分=2,000万円
✅結果
相続人 実際の取得額
👦 長男A 1,000万円
👧 長女B 2,000万円
❗すでに相続分を超えている場合は?
たとえば、長男Aが生前に2,500万円の贈与を受けていた場合
→ 法定相続分(2,000万円)を超えているため、相続分はゼロになります(民法903条2項)
🧠ポイント:本人の意思で除外も可能?
✋ 被相続人が「持ち戻ししなくていいよ」と明示的に意思表示していれば、その贈与は持ち戻しの対象外になります(民法903条3項)
📜たとえば、遺言で「Aに贈与した分は相続分から引かなくてよい」と書かれていればOKです!
💍夫婦間の住宅贈与は原則持ち戻しナシ!
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に居住用不動産(建物や敷地)を贈与または遺贈した場合は「持ち戻ししない意思があった」と推定されます!(民法903条4項)
これは、残された配偶者の生活保障を目的とした、特別な保護ルールです(´ω´)ノ
🧾「生計の資本」とは?
🔍「生計の資本」とは、被相続人から贈与された財産のうち、生活の基盤となるようなまとまった援助のことです。
単なる生活費ではなく、
🏠住宅購入費
💼事業開業資金
💍結婚資金 など
➡ 将来の自立や生活の出発点となる支援が対象です。
❗持ち戻し免除でも終わりじゃない!?
いくら「持ち戻し免除」されていても…
👉 他の相続人の「遺留分」を侵害することはNGです(;´Д`A ```
これはつまり、遺留分 > 持ち戻し免除という考え方になります(´゚д゚`)
たとえば、長男に贈与を集中させていても、法定相続人(配偶者・子など)の最低限の取り分(遺留分)は保障されます。
📢相続で「不公平!」とならないために…
トラブル回避には以下が超重要👇
💬 生前の援助は記録を残す
📜 遺言で意思をはっきり示す
👨⚖️ 専門家(司法書士・税理士など)に相談する
📞相続のご相談はお気軽に!
「これって特別受益になるの?」
「兄弟間でもめないように準備したい」
など、ご相談はいつでも承っております🏢
民法903条(特別受益者の相続分)
『条文内容』
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
🏠特別受益とは?相続分が変わるってホント?
こんにちは(´ω´)ノ
今回は、相続でもめやすい「特別受益」について、民法903条をもとにわかりやすく解説します✨
親から結婚資金や住宅購入資金の援助を受けたことがある方は…
👉 相続時に損する可能性があるかも!?Σ(゚Д゚;≡;゚д゚)
🧑⚖️民法903条とは?
被相続人(亡くなった方)から特別な贈与や遺贈を受けた相続人がいる場合、その相続人はその分を相続分から差し引かれるルールがあります。これを「特別受益の持ち戻し」といいます📘
💡具体例でスッキリ理解!
🏡登場人物
👴 父(被相続人)
👦 長男A:住宅購入時に1,000万円の援助を受けた
👧 長女B:特別な援助なし
🪙父の遺産総額:3,000万円
長男Aが過去に受けた1,000万円の援助は「特別受益」とみなされます(;´Д`)
🧮計算方法
持ち戻し財産=相続財産3,000万円+特別受益1,000万円=4,000万円
法定相続分(子が2人)=各2,000万円(4,000万円 ÷ 2)
長男Aの取り分=2,000万円-1,000万円(特別受益)=1,000万円
長女Bの取り分=2,000万円
✅結果
相続人 実際の取得額
👦 長男A 1,000万円
👧 長女B 2,000万円
❗すでに相続分を超えている場合は?
たとえば、長男Aが生前に2,500万円の贈与を受けていた場合
→ 法定相続分(2,000万円)を超えているため、相続分はゼロになります(民法903条2項)
🧠ポイント:本人の意思で除外も可能?
✋ 被相続人が「持ち戻ししなくていいよ」と明示的に意思表示していれば、その贈与は持ち戻しの対象外になります(民法903条3項)
📜たとえば、遺言で「Aに贈与した分は相続分から引かなくてよい」と書かれていればOKです!
💍夫婦間の住宅贈与は原則持ち戻しナシ!
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に居住用不動産(建物や敷地)を贈与または遺贈した場合は「持ち戻ししない意思があった」と推定されます!(民法903条4項)
これは、残された配偶者の生活保障を目的とした、特別な保護ルールです(´ω´)ノ
🧾「生計の資本」とは?
🔍「生計の資本」とは、被相続人から贈与された財産のうち、生活の基盤となるようなまとまった援助のことです。
単なる生活費ではなく、
🏠住宅購入費
💼事業開業資金
💍結婚資金 など
➡ 将来の自立や生活の出発点となる支援が対象です。
❗持ち戻し免除でも終わりじゃない!?
いくら「持ち戻し免除」されていても…
👉 他の相続人の「遺留分」を侵害することはNGです(;´Д`A ```
これはつまり、遺留分 > 持ち戻し免除という考え方になります(´゚д゚`)
たとえば、長男に贈与を集中させていても、法定相続人(配偶者・子など)の最低限の取り分(遺留分)は保障されます。
📢相続で「不公平!」とならないために…
トラブル回避には以下が超重要👇
💬 生前の援助は記録を残す
📜 遺言で意思をはっきり示す
👨⚖️ 専門家(司法書士・税理士など)に相談する
📞相続のご相談はお気軽に!
「これって特別受益になるの?」
「兄弟間でもめないように準備したい」
など、ご相談はいつでも承っております🏢