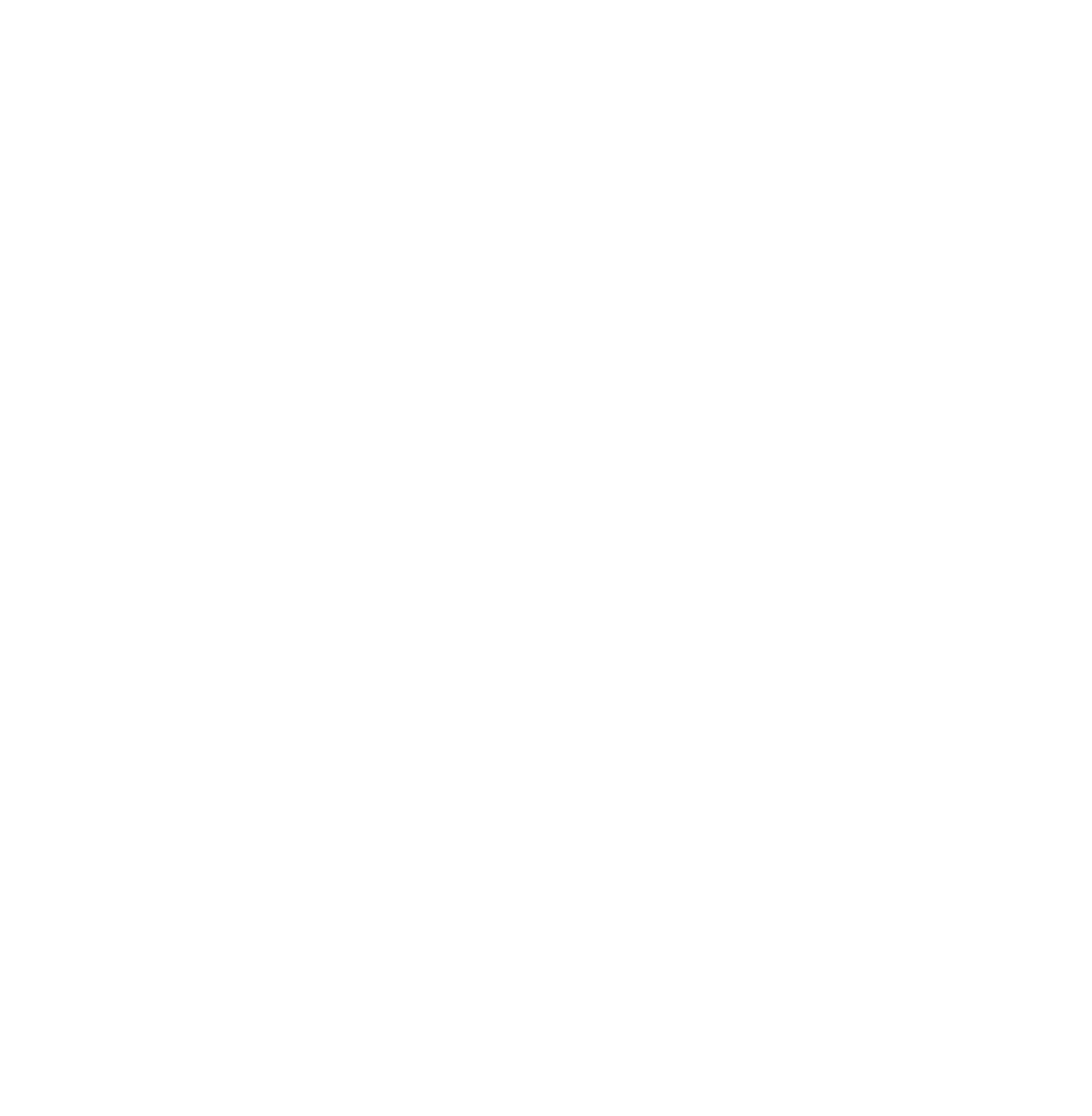ブログ
2025-06-15 14:03:24
民法904条の2(寄与分)
こんにちは!
今回は、相続に関するトラブルを防ぐための重要な仕組み、「寄与分(きよぶん)」について、わかりやすく解説します(´ω´)ノ
👪 寄与分ってなに?
「寄与分」とは、相続人の中で被相続人(亡くなった方)の財産を維持・増加させるために特別な貢献をした人がいた場合、その人の相続分を増やしてあげましょうというルールですφ(..)メモメモ
📘 たとえばこんなケース…
🧓 父(被相続人)…自営業を営んでいた
👨 長男…都会でサラリーマン
👩🦰 長女…父の自営業を手伝い、介護もしていた
🧓 父の遺産は3,000万円
普通に法定相続だと、兄妹それぞれ
👨 長男:1,500万円
👩🦰 長女:1,500万円
ですが…長女は10年にわたって父の事業を手伝い、介護までしていた!
👉 これは「特別の寄与」にあたる可能性があります(;´・ω・)
⚖️ じゃあどうなるの?
家族で話し合い(協議)をして、長女の寄与分を500万円と認めたとしましょう((´ω´)
💰 寄与分の計算はこうなります(´ω´)ノ
相続財産 3,000万円 - 寄与分 500万円 = 2,500万円
この2,500万円を法定相続で割る → 1,250万円ずつ
寄与者(長女)に寄与分500万円を加算
→ 長女は 1,250万円+500万円=1,750万円
→ 長男は 1,250万円
💥 話し合いがまとまらなかったら?
👩🦰 長女が「納得できない!」という場合は…
→ 家庭裁判所に請求することができます(第904条の2第2項)。
裁判所が、寄与の内容・時期・方法を見て、妥当な寄与分を決めてくれます(=゚ω゚)ノ
⚠️ 寄与分の限度
寄与分は、相続財産-遺贈財産の残額までと決まっています。
つまり、寄与分が相続された遺産全体を超えることはNGです(;´・ω・)
⏳ 寄与分に「時効」はあるのか?
結論から言えば…「寄与分」は金銭請求権(債権)ではありませんので、消滅時効は存在しないと解されてます(´ω´)ノ
あくまで「相続分を決めるための目安」であり、相続分の調整手段にすぎません😓
📘 したがって、債権のように○年で消滅するという「時効」の適用対象とはならないのです"(-""-)"
🚫 ただし、注意点もあります!
寄与分は遺産分割協議が成立するまでに主張しておく必要があります(;´・ω・)
❗なぜなら…遺産分割は全相続人および包括受遺者の合意により一度成立すれば、原則として後から修正ややり直しは事実上難しいと考えられるからです(;´・ω・)
なお、似たような制度に🟨 特別寄与料(民法第1050条)がありますが、こちらは📌 被相続人の親族が、相続人でないにもかかわらず療養看護などで特別の貢献をした場合、 金銭で請求できる制度です(=゚ω゚)ノ
❗でも、この制度には「期限」があります!
特別寄与料は、いつまでも請求できるわけではありません。
相続の開始 + 相続人を知った日から6か月以内に請求または、相続開始から1年以内に請求どちらか早い方が到来したら、もう請求できません💦
なお、6か月は消滅時効、1年は「除斥期間」です( ノД`)シクシク…
❌ 時効:時効完成前なら中断や更新が可能(例:裁判・催告など)
✅ 除斥期間:一切中断できず、過ぎたら完全に請求権消滅
📍ご相談は当事務所へ!
相続税申告・遺産分割協議・寄与分の相談など、経験豊富な専門家が親身にサポートいたします(; ・`д・´)
お気軽にお問い合わせください😊
民法904条の2(寄与分)
『条文内容』
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
こんにちは!
今回は、相続に関するトラブルを防ぐための重要な仕組み、「寄与分(きよぶん)」について、わかりやすく解説します(´ω´)ノ
👪 寄与分ってなに?
「寄与分」とは、相続人の中で被相続人(亡くなった方)の財産を維持・増加させるために特別な貢献をした人がいた場合、その人の相続分を増やしてあげましょうというルールですφ(..)メモメモ
📘 たとえばこんなケース…
🧓 父(被相続人)…自営業を営んでいた
👨 長男…都会でサラリーマン
👩🦰 長女…父の自営業を手伝い、介護もしていた
🧓 父の遺産は3,000万円
普通に法定相続だと、兄妹それぞれ
👨 長男:1,500万円
👩🦰 長女:1,500万円
ですが…長女は10年にわたって父の事業を手伝い、介護までしていた!
👉 これは「特別の寄与」にあたる可能性があります(;´・ω・)
⚖️ じゃあどうなるの?
家族で話し合い(協議)をして、長女の寄与分を500万円と認めたとしましょう((´ω´)
💰 寄与分の計算はこうなります(´ω´)ノ
相続財産 3,000万円 - 寄与分 500万円 = 2,500万円
この2,500万円を法定相続で割る → 1,250万円ずつ
寄与者(長女)に寄与分500万円を加算
→ 長女は 1,250万円+500万円=1,750万円
→ 長男は 1,250万円
💥 話し合いがまとまらなかったら?
👩🦰 長女が「納得できない!」という場合は…
→ 家庭裁判所に請求することができます(第904条の2第2項)。
裁判所が、寄与の内容・時期・方法を見て、妥当な寄与分を決めてくれます(=゚ω゚)ノ
⚠️ 寄与分の限度
寄与分は、相続財産-遺贈財産の残額までと決まっています。
つまり、寄与分が相続された遺産全体を超えることはNGです(;´・ω・)
⏳ 寄与分に「時効」はあるのか?
結論から言えば…「寄与分」は金銭請求権(債権)ではありませんので、消滅時効は存在しないと解されてます(´ω´)ノ
あくまで「相続分を決めるための目安」であり、相続分の調整手段にすぎません😓
📘 したがって、債権のように○年で消滅するという「時効」の適用対象とはならないのです"(-""-)"
🚫 ただし、注意点もあります!
寄与分は遺産分割協議が成立するまでに主張しておく必要があります(;´・ω・)
❗なぜなら…遺産分割は全相続人および包括受遺者の合意により一度成立すれば、原則として後から修正ややり直しは事実上難しいと考えられるからです(;´・ω・)
なお、似たような制度に🟨 特別寄与料(民法第1050条)がありますが、こちらは📌 被相続人の親族が、相続人でないにもかかわらず療養看護などで特別の貢献をした場合、 金銭で請求できる制度です(=゚ω゚)ノ
❗でも、この制度には「期限」があります!
特別寄与料は、いつまでも請求できるわけではありません。
相続の開始 + 相続人を知った日から6か月以内に請求または、相続開始から1年以内に請求どちらか早い方が到来したら、もう請求できません💦
なお、6か月は消滅時効、1年は「除斥期間」です( ノД`)シクシク…
❌ 時効:時効完成前なら中断や更新が可能(例:裁判・催告など)
✅ 除斥期間:一切中断できず、過ぎたら完全に請求権消滅
📍ご相談は当事務所へ!
相続税申告・遺産分割協議・寄与分の相談など、経験豊富な専門家が親身にサポートいたします(; ・`д・´)
お気軽にお問い合わせください😊