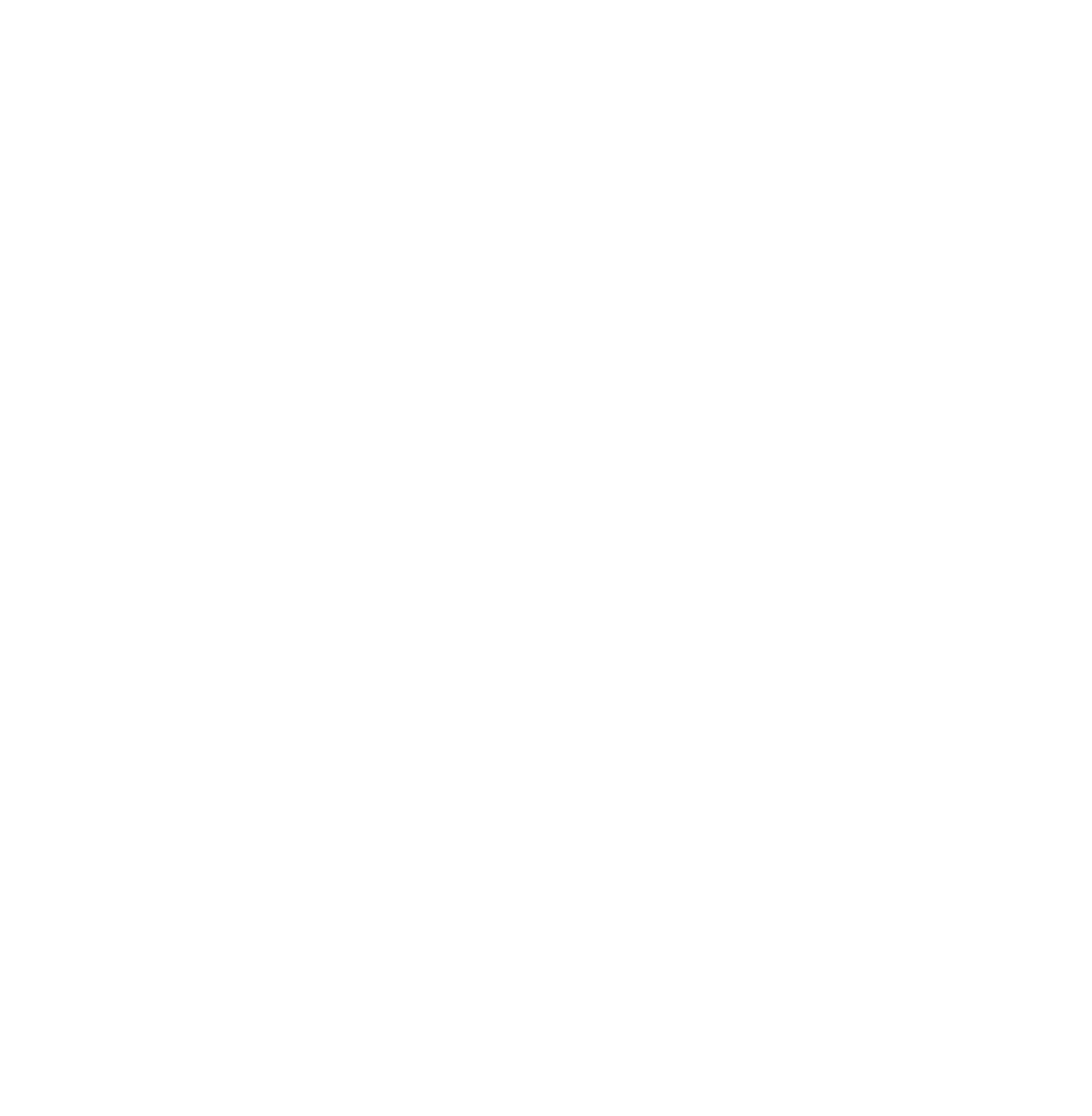ブログ
2025-06-23 19:25:12
民法904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)
🧓相続から10年経過…もう遺産は分けられない?
〜民法第904条の3をわかりやすく解説〜
🧭はじめに
「親が亡くなって10年以上放置していたけど、今さら遺産分けできるの(・・?」
「昔、兄が親の介護をしてたけど、それって今から主張できるの(・・?」
こうしたご相談が近年増えています(;´・ω・)
実は、2023年の民法改正により、「相続開始から10年が経過した遺産分割」には、ちょっとした注意点が加わりました( ..)φメモメモ
📘法律のポイント(民法904条の3)
相続開始から10年を過ぎたら…
✅ 遺産分割そのものはできるけど、
❌ 寄与分(介護した等)や特別受益(生前贈与など)の主張はできなくなる!
つまり、「誰がどれだけもらうべきか」という調整の主張ができなくなるのです💀
🧠実際にはどうなる?
✅ 10年以内の場合(通常のケース)
👴 お父さんが亡くなって5年後に遺産分割開始
👦 長男が「介護したから多くもらいたい」と主張
🧑⚖️ 家庭裁判所は「寄与分あり」として長男に多く配分
→ ✅ 調整ありの具体的相続分が認められます!
❌ 10年経過後のケース
👴 お父さんが亡くなって12年後に分割しようとした
👧 長女が「私は生前に家をもらってるから減額で」と主張
⚖️ 民法904条の3により、その主張はもうできません!
→ ✋ つまり、「法定相続分」で割り切るしかないのです(1/2ずつ、など)
💬じゃあ話し合いで多くもらうこともダメ?
いいえ、相続人全員の合意があれば、自由な分け方も可能です。
ただし、その際に誰かが「納得できない」「法定相続分でないとダメ」と言い出せば、調整の根拠がないため強制できなくなるのです(;´・ω・)
🕰️過去の相続にも影響?
はい、実はこの改正には「経過措置」があり、すでに相続が発生しているケースにも効力が及びます(;^_^A
📘経過措置のポイント(附則第3条)
✅① 相続が令和5年4月1日に発生した場合
🗓 たとえば:
被相続人が2023年5月1日に死亡 → 通常通り10年ルールが適用
🔚⇒ 2033年5月1日までに分割協議しないと、寄与分等が主張できなくなる!
✅② 相続が令和5年4月1日【より前】に発生していた場合
🗓 たとえば:
被相続人が2010年に死亡していても、
🛡 改正法は「即時には適用しない」ように、5年間の猶予期間(令和10年4月1日まで)を設けています!
🔚⇒ 相続発生から10年経過時または施行時から5年経過時(令和10年4月1日)のいずれか遅い方となります(;´・ω・)
📝おわりに
「どうせ親族だからいつでも話せる」と思って後回しにしていると、10年を過ぎてしまい、大事な主張ができなくなる恐れがあります(´・ω・`)
遺産の話は早いうちに、できれば相続開始から数年以内に整理しましょう(;´・ω・)
不安な場合は、早めに専門家に相談するのがおすすめです(´ω´)ノ
民法904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)
『条文内容』
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
🧓相続から10年経過…もう遺産は分けられない?
〜民法第904条の3をわかりやすく解説〜
🧭はじめに
「親が亡くなって10年以上放置していたけど、今さら遺産分けできるの(・・?」
「昔、兄が親の介護をしてたけど、それって今から主張できるの(・・?」
こうしたご相談が近年増えています(;´・ω・)
実は、2023年の民法改正により、「相続開始から10年が経過した遺産分割」には、ちょっとした注意点が加わりました( ..)φメモメモ
📘法律のポイント(民法904条の3)
相続開始から10年を過ぎたら…
✅ 遺産分割そのものはできるけど、
❌ 寄与分(介護した等)や特別受益(生前贈与など)の主張はできなくなる!
つまり、「誰がどれだけもらうべきか」という調整の主張ができなくなるのです💀
🧠実際にはどうなる?
✅ 10年以内の場合(通常のケース)
👴 お父さんが亡くなって5年後に遺産分割開始
👦 長男が「介護したから多くもらいたい」と主張
🧑⚖️ 家庭裁判所は「寄与分あり」として長男に多く配分
→ ✅ 調整ありの具体的相続分が認められます!
❌ 10年経過後のケース
👴 お父さんが亡くなって12年後に分割しようとした
👧 長女が「私は生前に家をもらってるから減額で」と主張
⚖️ 民法904条の3により、その主張はもうできません!
→ ✋ つまり、「法定相続分」で割り切るしかないのです(1/2ずつ、など)
💬じゃあ話し合いで多くもらうこともダメ?
いいえ、相続人全員の合意があれば、自由な分け方も可能です。
ただし、その際に誰かが「納得できない」「法定相続分でないとダメ」と言い出せば、調整の根拠がないため強制できなくなるのです(;´・ω・)
🕰️過去の相続にも影響?
はい、実はこの改正には「経過措置」があり、すでに相続が発生しているケースにも効力が及びます(;^_^A
📘経過措置のポイント(附則第3条)
✅① 相続が令和5年4月1日に発生した場合
🗓 たとえば:
被相続人が2023年5月1日に死亡 → 通常通り10年ルールが適用
🔚⇒ 2033年5月1日までに分割協議しないと、寄与分等が主張できなくなる!
✅② 相続が令和5年4月1日【より前】に発生していた場合
🗓 たとえば:
被相続人が2010年に死亡していても、
🛡 改正法は「即時には適用しない」ように、5年間の猶予期間(令和10年4月1日まで)を設けています!
🔚⇒ 相続発生から10年経過時または施行時から5年経過時(令和10年4月1日)のいずれか遅い方となります(;´・ω・)
📝おわりに
「どうせ親族だからいつでも話せる」と思って後回しにしていると、10年を過ぎてしまい、大事な主張ができなくなる恐れがあります(´・ω・`)
遺産の話は早いうちに、できれば相続開始から数年以内に整理しましょう(;´・ω・)
不安な場合は、早めに専門家に相談するのがおすすめです(´ω´)ノ