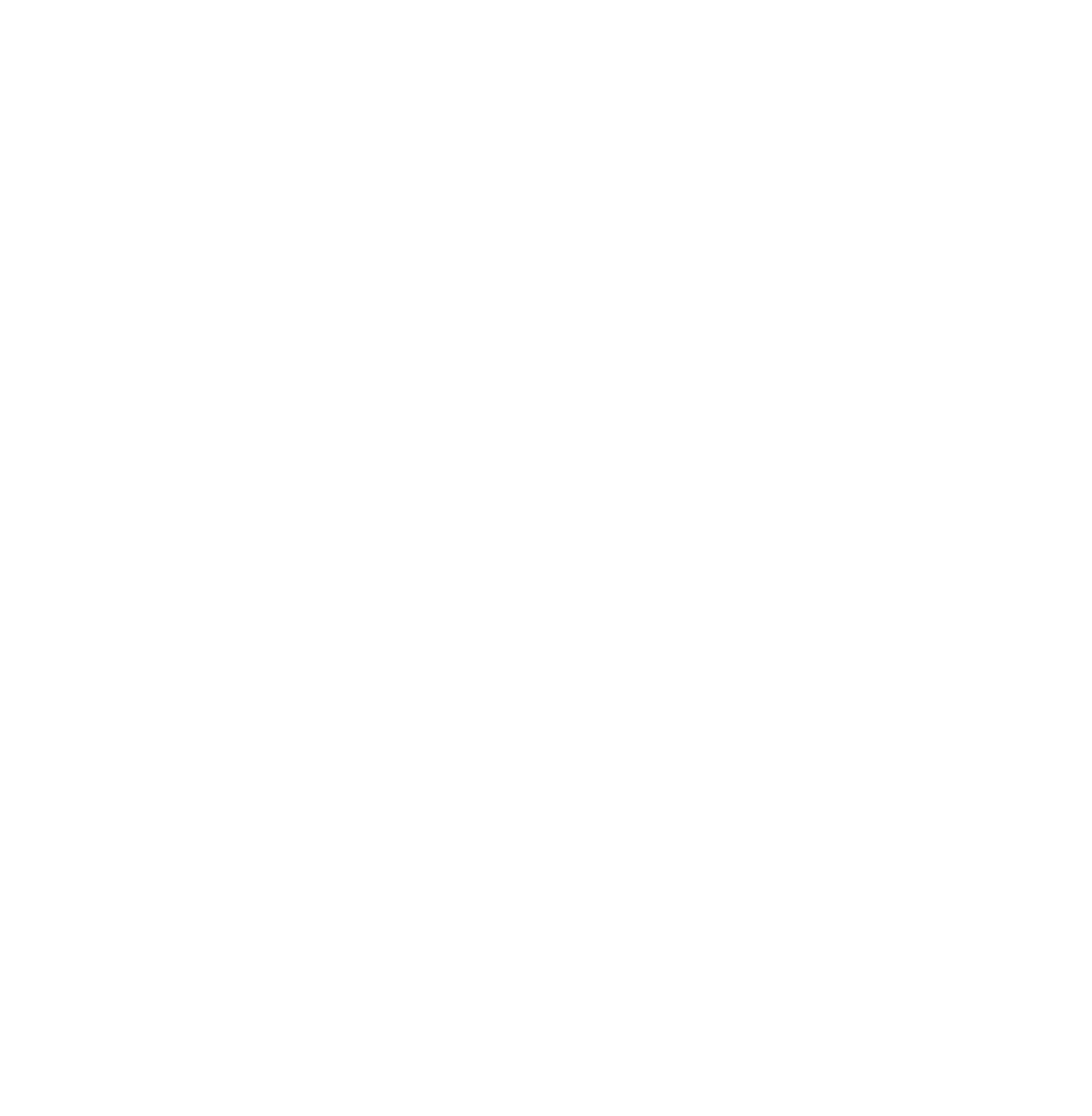ブログ
2025-06-27 09:25:58
民法905条(相続分の取戻権)
⚖️【民法第905条】相続分の取戻権とは?
~相続分が第三者に譲渡されたとき、他の相続人はどうできるのか~
こんにちは(´ω´)ノ
今回は、共同相続人の一人が自らの相続分を第三者に譲渡した場合に、他の相続人がその相続分を取り戻せるかどうかについて定めた、民法第905条(相続分の取戻権)の条文内容を解説します。
🔍 条文のポイント解説
✅相続分を第三者に譲渡することは可能(・・?
条文は、「共同相続人の一人が第三者に相続分を譲渡したとき」と前提しています。つまり、相続分の全部または一部の譲渡自体が認められていることが前提です(;´・ω・)
この「相続分」とは、遺産全体(積極財産+消極財産)に対する割合的持分であり、不動産や預金など特定の財産ではなく包括的な相続人としての地位の一部を指します(´ω´)ノ
✅取戻権の要件
取戻権を行使できるのは、次の3要件を満たした場合です( ..)φメモメモ
① 譲渡時期 遺産の分割前であること
② 譲渡の相手は第三者(共同相続人以外ならだれでも可)であること
③ 取戻権を行使するのは他の共同相続人であること
つまり、共同相続人同士の相続分の譲渡にはこの条文は適用されません。
✅「価額および費用を償還して」譲り受けるとは?
「価額」=第三者が相続分を取得するのに支払った金額
「費用」=譲渡に伴って第三者が負担した合理的なコスト(例:登記費用、契約書作成費など)
取戻しを希望する相続人は、これらを支払うことで譲渡された相続分を取得することが可能になります(; ・`д・´)
✅行使期間は「1か月」
この取戻権は、譲渡があったことを知ってから1か月以内に行使しなければならないとされています(第2項)。
この期間を過ぎると、相続分の譲渡は確定し、第三者が相続人と同等の権利を持つことになります💦なお、相続分の全部を譲渡した人は、相続人としての立場を失います(; ・`д・´)
🧭 取戻権の趣旨
本条文の趣旨は、遺産分割の協議に第三者が介入することによる混乱を避け、円滑な分割を図ることにあります(;^_^A
相続は家族間の問題であり、突然外部の第三者が「相続人として」協議に加わることは他の相続人にとって大きな不利益や違和感を伴うことがあります(;´・ω・)
そこで、一定の要件のもと、他の相続人に“買い戻し”のような権利を認めることでバランスをとっているわけです(^^♪
🧾 実務上の留意点
この取戻権は権利であり義務ではありません。必ず行使する必要はありません。行使の意思表示だけで効力があるとされています(判例・通説)。
なお、取戻しが行われた場合、第三者は原則として相続人としての地位を失います(;^_^A
相続に関する条文は抽象的でわかりづらい部分も多いですが、この905条は共同相続人の地位を守るための重要なルールです(´ω´)ノ
「知らぬ間に相続分が他人に渡っていた…」という場面では、冷静に条文の趣旨を理解し、速やかに対応することが求められます☺
🎯 まとめ
家族の相続分が「知らない他人」に流れるのを防ぐための、大事なルールです⚖️
特に不動産や事業資産などが絡む相続では、要チェックですね✅
「知らなかった」では済まされない1か月ルール、相続人の一人が勝手に動いたときには、すぐに対応を!🏃♂️💨
ご相談・対策はお早めにどうぞ😊
📩 中村裕史税理士事務所までお気軽に!
民法905条(相続分の取戻権)
『条文内容』
(相続分の取戻権)
第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
(相続分の取戻権)
第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
⚖️【民法第905条】相続分の取戻権とは?
~相続分が第三者に譲渡されたとき、他の相続人はどうできるのか~
こんにちは(´ω´)ノ
今回は、共同相続人の一人が自らの相続分を第三者に譲渡した場合に、他の相続人がその相続分を取り戻せるかどうかについて定めた、民法第905条(相続分の取戻権)の条文内容を解説します。
🔍 条文のポイント解説
✅相続分を第三者に譲渡することは可能(・・?
条文は、「共同相続人の一人が第三者に相続分を譲渡したとき」と前提しています。つまり、相続分の全部または一部の譲渡自体が認められていることが前提です(;´・ω・)
この「相続分」とは、遺産全体(積極財産+消極財産)に対する割合的持分であり、不動産や預金など特定の財産ではなく包括的な相続人としての地位の一部を指します(´ω´)ノ
✅取戻権の要件
取戻権を行使できるのは、次の3要件を満たした場合です( ..)φメモメモ
① 譲渡時期 遺産の分割前であること
② 譲渡の相手は第三者(共同相続人以外ならだれでも可)であること
③ 取戻権を行使するのは他の共同相続人であること
つまり、共同相続人同士の相続分の譲渡にはこの条文は適用されません。
✅「価額および費用を償還して」譲り受けるとは?
「価額」=第三者が相続分を取得するのに支払った金額
「費用」=譲渡に伴って第三者が負担した合理的なコスト(例:登記費用、契約書作成費など)
取戻しを希望する相続人は、これらを支払うことで譲渡された相続分を取得することが可能になります(; ・`д・´)
✅行使期間は「1か月」
この取戻権は、譲渡があったことを知ってから1か月以内に行使しなければならないとされています(第2項)。
この期間を過ぎると、相続分の譲渡は確定し、第三者が相続人と同等の権利を持つことになります💦なお、相続分の全部を譲渡した人は、相続人としての立場を失います(; ・`д・´)
🧭 取戻権の趣旨
本条文の趣旨は、遺産分割の協議に第三者が介入することによる混乱を避け、円滑な分割を図ることにあります(;^_^A
相続は家族間の問題であり、突然外部の第三者が「相続人として」協議に加わることは他の相続人にとって大きな不利益や違和感を伴うことがあります(;´・ω・)
そこで、一定の要件のもと、他の相続人に“買い戻し”のような権利を認めることでバランスをとっているわけです(^^♪
🧾 実務上の留意点
この取戻権は権利であり義務ではありません。必ず行使する必要はありません。行使の意思表示だけで効力があるとされています(判例・通説)。
なお、取戻しが行われた場合、第三者は原則として相続人としての地位を失います(;^_^A
相続に関する条文は抽象的でわかりづらい部分も多いですが、この905条は共同相続人の地位を守るための重要なルールです(´ω´)ノ
「知らぬ間に相続分が他人に渡っていた…」という場面では、冷静に条文の趣旨を理解し、速やかに対応することが求められます☺
🎯 まとめ
家族の相続分が「知らない他人」に流れるのを防ぐための、大事なルールです⚖️
特に不動産や事業資産などが絡む相続では、要チェックですね✅
「知らなかった」では済まされない1か月ルール、相続人の一人が勝手に動いたときには、すぐに対応を!🏃♂️💨
ご相談・対策はお早めにどうぞ😊
📩 中村裕史税理士事務所までお気軽に!